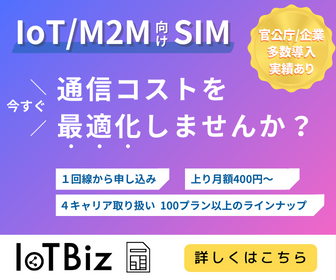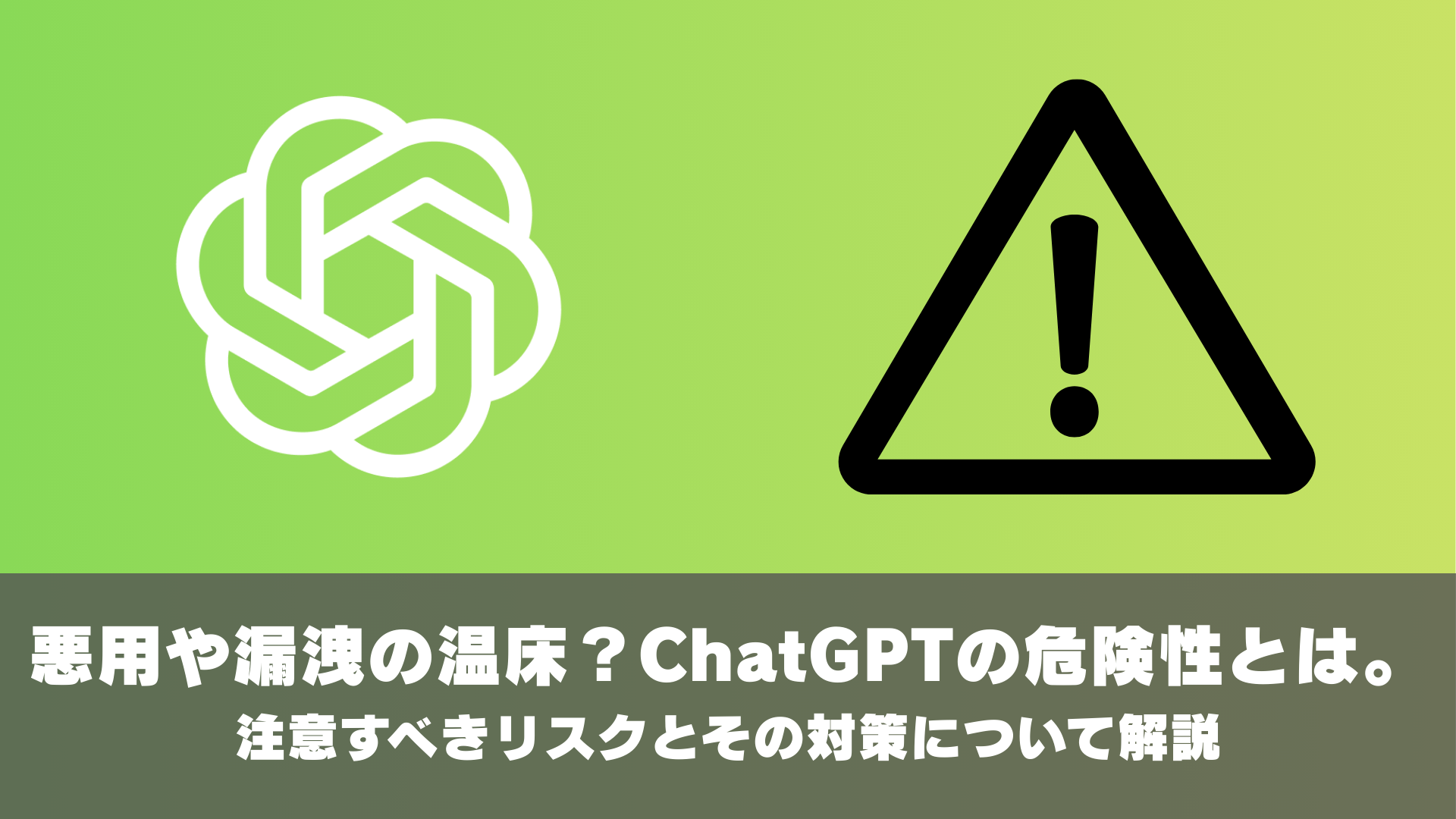ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違い!メリット・デメリット、活用事例も解説
ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違い!メリット・デメリット、活用事例も解説

近年では、企業だけでなく個人でもウェブサイトやウェブサービスを提供する際に、クラウドコンピューティングを活用することが一般的になりました。この記事では、クラウドコンピューティングの活用方法である「ハイブリッドクラウド」と「マルチクラウド」について詳しく解説します。これらの手法は、企業や個人が効果的にリソースを管理し、ビジネスの成果を最大化するための重要な戦略です。 ハイブリッドクラウドとマルチクラウドは、それぞれ異なる利点と適用範囲を持っていますが、どちらの手法も組織や個人がクラウドリソースを最適化し、ビジネスの成果を最大限に引き出すための重要な戦略となります。適切な戦略を選択し、クラウドコンピューティングの利点を最大限に活用しましょう。
目次
ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違い
まずは、ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違いを比較しながら、違いを紹介します。
クラウドコンピューティングの活用方法は、「ハイブリッドクラウド」「マルチクラウド」の2種類に分けることができます。

| ハイブリッドクラウド | マルチクラウド | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・互換性の高く利用することが可能 | ・自社に最適なクラウド環境の構築が可能 |
| メリット | ・導入コストや運用コストが少ない ・クラウドの負担を分散可能 ・高度なセキュリティを構築しやすい |
・用途に応じたカスタマイズが可能 ・ベンダー依存度を低減 ・リスクの分散 |
| デメリット | ・システム設計と構築が複雑 ・運用ハードルが高い |
・運用コストが高い ・セキュリティリスクが高い |
ハイブリッドクラウドはパブリックとプライベートの組み合わせで均衡を取り、セキュリティを強化します。一方で、マルチクラウドは複数ベンダーを利用し、柔軟な運用環境を実現しますが、コストとセキュリティに関する検討が必要です。企業は用途や要件に応じて、適切な戦略を選択することが重要です。
ハイブリッドクラウド
ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて運用する手法です。このアプローチは、導入コストや運用コストを最小限に抑えつつ、クラウドの負担を均等に分散し、高度なセキュリティを構築しやすい特長があります。ただし、両者を併用するため、システム設計と構築が複雑になり、運用ハードルが上がる可能性があります。
マルチクラウド
マルチクラウドは、異なるクラウドサービス提供業者のクラウドを組み合わせ、最適な運用環境を構築する手法です。この手法の利点は、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能であり、ベンダーへの依存度が低くなり、ベンダーロックインを回避できることです。ただし、複数のクラウドサービスを利用することで運用コストが上昇し、セキュリティリスクが増大する可能性があります。
そもそもクラウド(クラウドコンピューティング)とは
クラウドコンピューティング(cloud computing)とは、「クラウド」「クラウドサービス」「クラウドコンピューティングサービス」とも呼ばれ、インターネットなどのネットワークを通して、クラウドサービス提供事業者の提供するサービスを利用する仕組みです。
提供される機能には、サーバーやストレージ、データベース、アプリケーションなどがあります。
「クラウドコンピューティング」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
『クラウドコンピューティングとは?仕組みやメリット、課題を徹底的に紹介!』
ハイブリッドクラウドとは
ハイブリッドクラウドとは、クラウドコンピューティングの手法で、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて運用します。これは、異なるクラウド環境を柔軟に利用するための手段となります。
ハイブリッドクラウド = 併用(パブリッククラウド + プライベートクラウド)
典型的な利用例としては、機密データや社内開発者のリソースにはプライベートクラウドを使用し、Webサイトのトラフィックや運用データにはパブリッククラウドを組み合わせ、目的に応じた最適なクラウド環境を構築することが挙げられます。
「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
『パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いやメリット・デメリット、活用事例を徹底解説』
ハイブリッドクラウドの特徴
(1)複数クラウドの統合利用
ハイブリッドクラウドは、異なるクラウド環境やサービスを同時に利用可能です。これにより、企業は多様なクラウドリソースを最大限に活用できます。
(2)実装モデル
ハイブリッドクラウドはクラウド環境の構築方法として位置づけられ、各環境やサービスを統合し、単一のシステムを構築します。
(3)総合接続の必要性
異なるクラウド環境やサービスを統合するには、クラウドの総合接続が不可欠です。これにより、シームレスなデータおよびサービスの連携が実現されます。
ハイブリッドクラウドのメリット
(1)高い柔軟性
ハイブリッドクラウドは、柔軟性が非常に高いです。規制要件やレイテンシーの問題から生じる制約に対処するため、データの一部をオンプレミスのインフラで運用し、他の部分をパブリッククラウドで運用することが可能です。
(2)リモートアクセスの可能性
在宅勤務を採用する場合、ハイブリッドクラウドはリモートメンバーがオンプレミスのデータやアプリにアクセスできるようにし、柔軟な業務環境を提供できます。
(3)高いスケーラビリティ
ハイブリッドクラウドでは、需要が急増した場合でもハードウェアの過剰な準備を回避し、アプリやサービスに迅速に対応できます。これにより、顧客満足度を確保することができます。
ハイブリッドクラウドのデメリット
(1)導入の複雑性
ハイブリッドクラウド環境の導入と維持は、困難な場合があります。異なるクラウド環境の互換性を確認するために経験豊富なクラウドアーキテクトのスキルが必要であり、オンプレミスのインフラも管理が必要です。
(2)可視化の難しさ
クラウド環境は複雑で、ハイブリッドクラウドでは2つの異なる環境を把握することが難しいです。全体のクラウドシステムを明確に把握することは困難です。
(3)ネットワークのボトルネック
プライベートクラウドとパブリッククラウドのデータ転送時に、ネットワークがボトルネックになる可能性があります。インターネット経由でのデータ転送は遅延の原因となります。
ハイブリッドクラウドの注意点
ハイブリッドクラウドの注意点は、前述のデメリットで述べた「システム設計と構築が複雑化し、運用ハードルが上がる」という点です。
はじめに、ハイブリッドクラウドを検討する際には、クラウドコンピューティングの設計に長けた専門エンジニアが設計を行うことが必須です。その後の構築、運用においても、クラウドコンピューティングの開発・運用に長けたエンジニア人材が管理していく必要があります。
また、前述のメリットで述べた「高度なセキュリティを構築しやすい」という点に関しても、少なくとも一部は、オープンネットワークにつながるパブリッククラウドを利用するため、オンプレミスでの運用時と比較すると、しっかりとしたセキュリティの構築と設定が必要となります。セキュリティ面に関しても、セキュリティに長けた人材が設計と構築をする必要があります。
ハイブリッドクラウドの活用事例3選
ハイブリッドクラウドの活用方法は、多岐に渡りますが、その中でも主な活用方法を3つ紹介します。
(1)BCP対策としての活用
ハイブリッドクラウドは、BCP(事業継続計画)対策として、多く活用されています。BCP(事業継続計画)とは、テロや災害、システム障害など危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、事業やサービス、会社を継続し続けられるようにするための計画として、経営の重要な指標の一つとなっています。
このBCPの観点から見ると、「プライベートクラウド」と「パブリッククラウド」を併用するハイブリッドクラウドは、データ分散管理しているため、万が一、パブリッククラウドが危機的状況下に置かれた場合でも、プライベートクラウドにデータバックアップをしておけば、迅速に緊急対応することができます。プライベートクラウドが危機的状況下に置かれた場合でも、同様の対応をすることができます。
水環境分野における大手総合エンジニアリング会社のメタウォーター株式会社では、ハイブリッドクラウドを活用し、災害発生時には、パブリッククラウド(富士通が提供するCloud Volumes ONTAP)を利用することで、クラウド上のデータを元に業務再開を可能にするような対策を講じています。
(参考)ストレージ導入事例 メタウォーター株式会社様|富士通
(2)システム移行としての活用
ハイブリッドクラウドは、システム移行の場面でも多く活用されています。例えば、CRM(顧客関係管理)をクラウド移行する場合などは、重要度の高い顧客データをHubSpotやSalesforceの専用のCRMツールへ移行し、それ以外の顧客データをAWS (Amazon Web Services)やMicrosoft Azureなどに移行するなどの活用が可能です。
神奈川トヨタ自動車株式会社では、「Windows Server 2003」のリプレイスにあたり、全サーバーのクラウド化を行いました。その際に活用したのが、SalesforceとAWS (Amazon Web Services)のハイブリッドクラウドです。
(参考)クラウド利用の進化形 ハイブリッドクラウド活用事例と導入ポイント|テラスカイクラウドレポート
(3)システム負荷の分散としての活用
ハイブリッドクラウドは、システム負荷の分散としても多く活用されています。例えば、一度にたくさんのアクセスがウェブサイトに集中したりすると、サーバーがリクエストを処理しきれずにダウンしてしまうことがありますが、ハイブリッドクラウドで負荷分散を行うことで、このような場合にも、リソースの増減が十分に対応できるパブリッククラウドを活用することでシステムの負荷を分散させることができます。
アメリカミシガン州に本社を置くアパレル会社のCarhartt(カーハート)は、オンライン販売と小売店を統合して直接販売を増やすことにより、従来の卸売ビジネスモデルから新たなビジネスモデルへと変革を行なっていましたが、進化の早いテクノロジーの要件に対応するため、SAPシステムをアップグレードしたいと考えていましたが、これまでのシステムではかなりの負荷がかかるシステム設計となっていたためMicrosoft Azureを活用して、ハイブリッドクラウド化を行い、システム負荷の分散を実施しました。
(参考)Microsoft Customer Story-Carhartt gains business agility, supports rapid business growth with SAP solutions on Azure and Teams|Microsoft
マルチクラウドとは
クラウドコンピューティングの1つの活用方法であるマルチクラウドについて紹介します。

マルチクラウドとは、複数のクラウドサービスを組み合わせて、最適な運用環境を構築するクラウドの利用形態を指します。
特徴としては、以下の3つの特徴があります。
・複数クラウドサービスの組み合わせ
マルチクラウドでは、複数の異なるクラウドサービス提供業者のクラウドサービスを組み合わせます。例えば、AWSとMicrosoft Azureを同時に使用する場合が挙げられます。
・最適な環境の構築
企業はそれぞれのクラウドサービスのメリットやデメリットを活かし、自社にとって最適な運用環境を構築します。これにより、クラウドシステムを利用する際の利便性を向上させることが可能です。
・データ通信量の分散
マルチクラウドの採用により、データ通信量が複数のクラウドに分散されます。これにより、特定のサービスやアプリからのアクセスが集中してデータが重くなることを防ぎます。
例えば、AWS (Amazon Web Services)と、Microsoft Azureを組み合わせて運用環境を構築するという場合は、まさにマルチクラウドにあたります。
『AWS IoT Coreとは?仕組みや機能、Azureとの違いを解説』
『Microsoft Azure IoT Hubとは?仕組みや機能、料金、AWSとの違いを解説』
クラウドは実装モデルによって「パブリッククラウド」「プライベートクラウド」「ハイブリッドクラウド」に分類されます。これは、「クラウド環境をどう実現しているか」で分類したものであり、マルチクラウドとはやや次元が異なる言葉です。また、「IaaS」や「PaaS」「SaaS」は、「クラウドから何を提供しているか」を表しており、いわばサービスモデルです。
『SaaS、PaaS、IaaS(HaaS)とは?特徴やメリット・デメリット、違い、関係性を解説』
マルチクラウドのメリット
用途に応じたカスタマイズが可能
マルチクラウドを採用することで、各クラウドサービスの利点を最大限に活用し、業務プロセスを効率的にカスタマイズできます。
ベンダー依存度を低減
複数のプロバイダーを利用することで、特定のベンダーに依存せず、柔軟にサービスを組み合わせることができます。これにより、ベンダーロックインを回避し、ビジネスに対する柔軟性が向上します。
リスクの分散
複数のクラウドサービスを利用することで、リスクを分散させることができます。一つのクラウドサービスに障害が発生しても、他のクラウドサービスが引き続き稼働し、業務の中断を最小限に抑えます。
マルチクラウドのデメリット
運用コストが高い
複数のプロバイダーを利用するため、管理や調整にかかる運用コストが増加します。また、マルチクラウド管理ツールへの投資も必要となり、これがコストを押し上げる要因となります。
セキュリティリスクが高い
ベンダー間でセキュリティ基準が異なる場合、システム全体として統一されたセキュリティが確保されない可能性があります。これにより、セキュリティリスクが高まります。
マルチクラウドの活用事例4選
マルチクラウドの活用方法は、多岐に渡りますが、その中でも主な活用方法を4つ紹介します。
(1)グローバルビジネスで、リージョンや国ごとにクラウドを使い分け
マルチクラウドは、複数の国や地域に事業展開をしているグローバル企業で、リージョンや国ごとに最適なクラウドを選定し使い分ける方法があります。
アパレルのGLOBAL WORK(グローバルワーク)やniko and…(ニコアンド)、LOWRYS FARM(ローリーズファーム)などを、国内1,342店舗と中国・その他海外などグローバルに展開する株式会社アダストリアの中国リージョンでは、中国国内で活用がしやすいAlibaba Cloud(アリババクラウド)を採用しています。
(参考)マルチクラウドソリューション導入事例:株式会社アダストリア様|株式会社日立システムズ
(2)提供サービスや事業ごとにクラウドを使い分け
マルチクラウドは、複数の事業やサービスを展開する企業では、事業ごとやサービスごとに最適なクラウドを選択し、それぞれのクラウドを活用する方法もあります。
(3)社内用と顧客向けサービスでクラウドを使い分け
マルチクラウドは、社内用サービスやデータに専用のクラウドを選択し、顧客向けのサービスや事業には、それに適した専用のクラウドを選択するという方法もあります。
アパレルのGLOBAL WORK(グローバルワーク)やniko and…(ニコアンド)、LOWRYS FARM(ローリーズファーム)などを、国内1,342店舗と中国・その他海外などグローバルに展開する株式会社アダストリアでは、国内各店舗では、社内用や顧客用など利用用途に合わせてメジャークラウド、オンプレミス、データセンターを使い分けています。
(参考)マルチクラウドソリューション導入事例:株式会社アダストリア様|株式会社日立システムズ
(4)BCP対策としてクラウドを使い分け
ハイブリッドクラウドと同様にマルチクラウドは、BCP(事業継続計画)対策として、多く活用されています。BCP(事業継続計画)とは、テロや災害、システム障害など危機的状況下に置かれた場合でも、重要な業務が継続できる方策を用意し、事業やサービス、会社を継続し続けられるようにするための計画として、経営の重要な指標の一つとなっています。
このBCPの観点から見ると、1つのクラウドサービスに依存せずに、複数のクラウドサービスを利用することで、1つのクラウドで大規模障害に陥ったときにも、別クラウドで迅速に緊急対応することができます。
ヤマトホールディングス株式会社は、3つの事業構造改革として、「宅急便デジタルトランスフォーメーション(DX)」「ECエコシステムの確立」「法人向け物流事業の強化」を実践した際にも、クラウドサービスの大規模障害に備えて、1つのクラウドサービスに依存しないマルチクラウドの体制を構築しています。
(参考)マルチクラウド実践企業から学ぶ最新クラウド事情 ──Yamato DX Night #2レポート|TECH PLAY Magazine
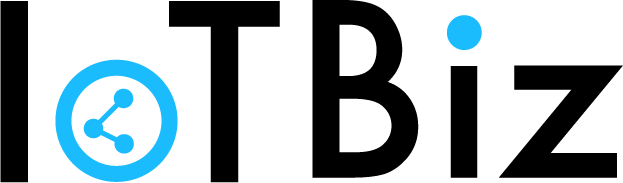
IoTBiz編集部
2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。
関連記事
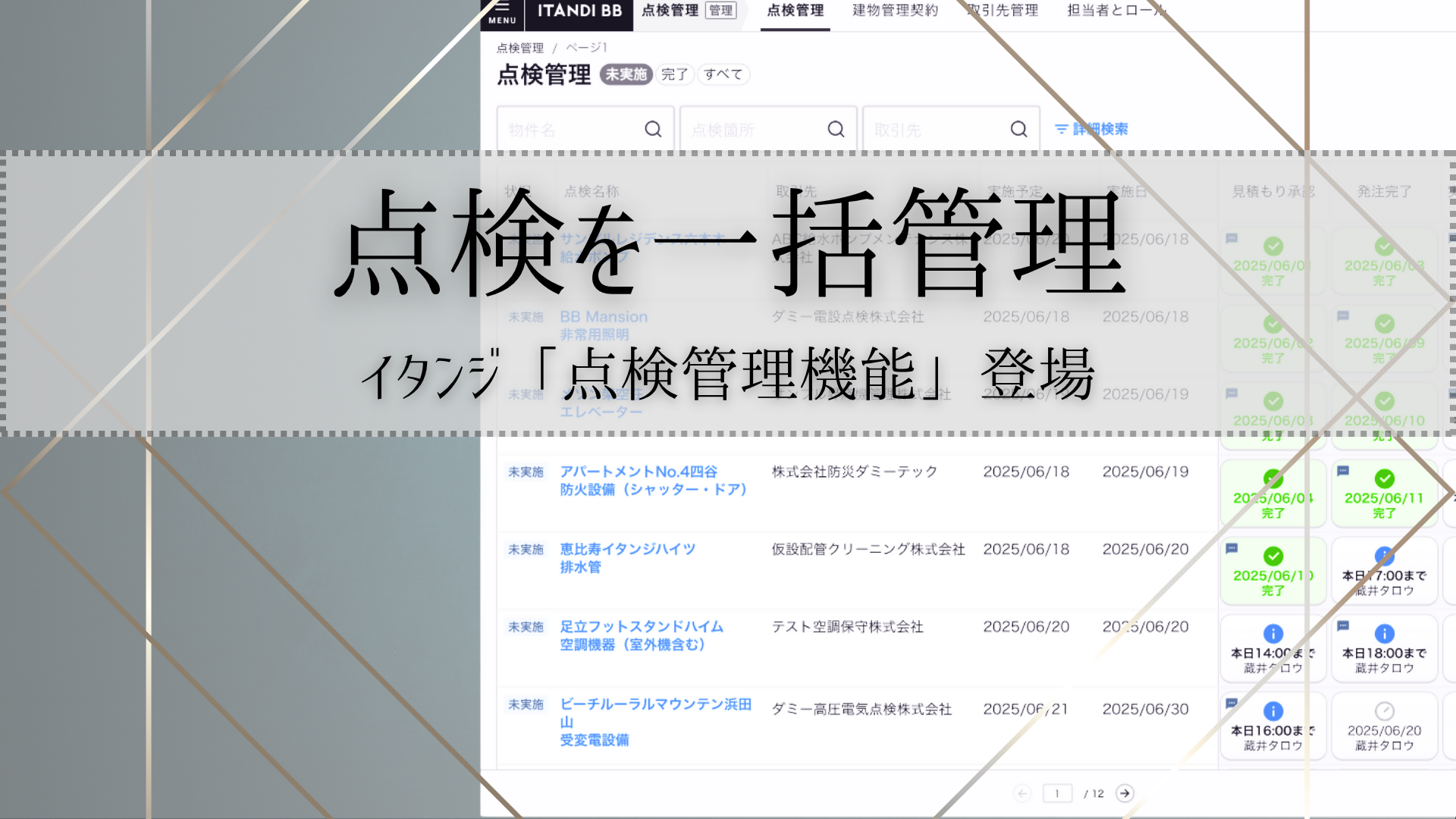
ニュース
クラウド
SaaS
この記事では、イタンジ株式会社から提供されている賃貸管理システム「ITANDI管理クラウド」において、建物点検の進行管理を一元化する新機能「点検管理機能」について紹介しています。
2025-08-07
2min
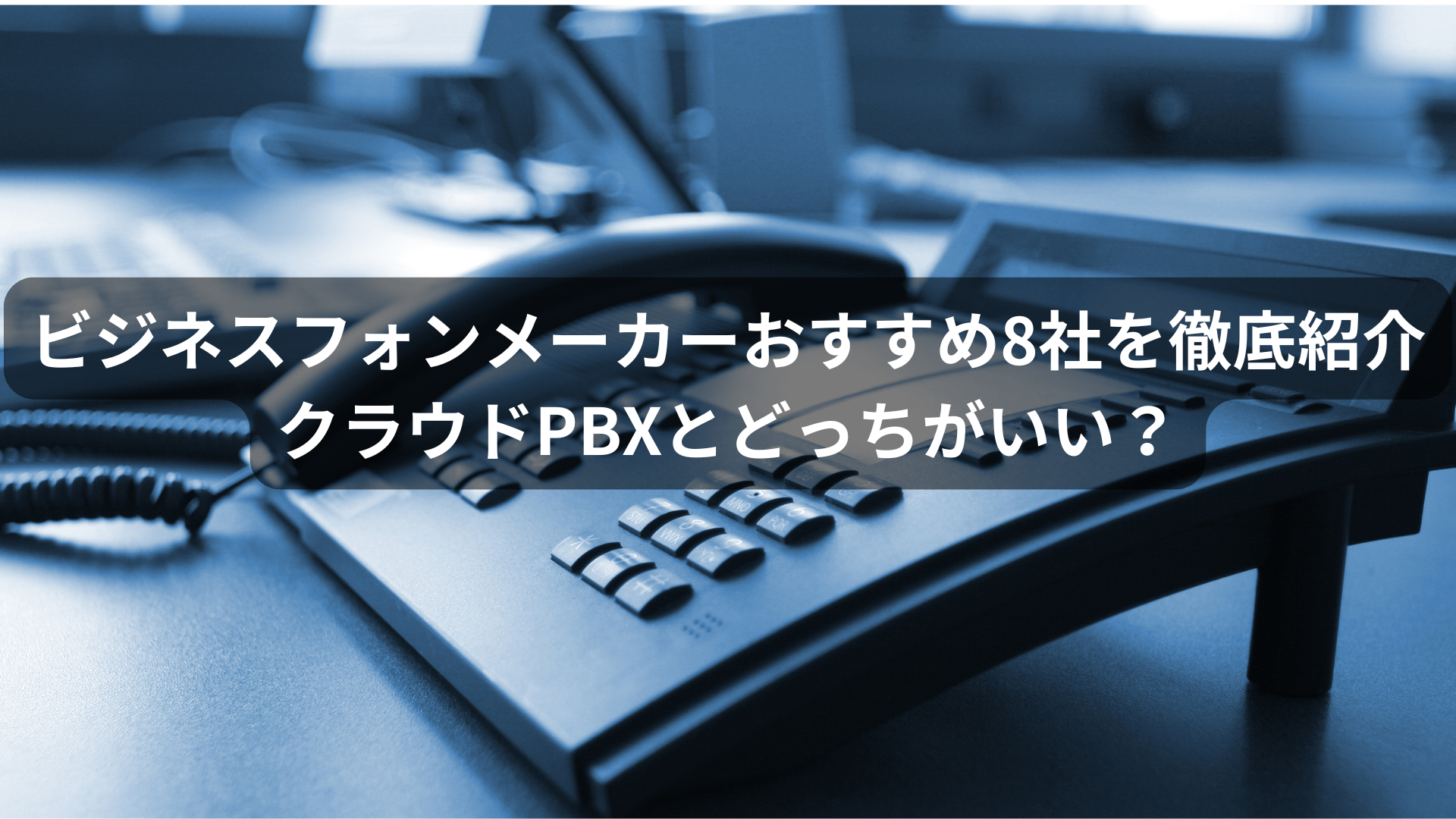
クラウド
本記事ではビジネスフォンおすすめ8社(NTT・NEC・SAXA・日立・NAKAYO・IWATSU)のビジネスフォンを徹底解説します。ビジネスフォンとクラウドPBXの違いやビジネスフォン選びのポイントも開設しているので是非ビジネスフォン選びの参考にしてください。
2025-03-19
5min
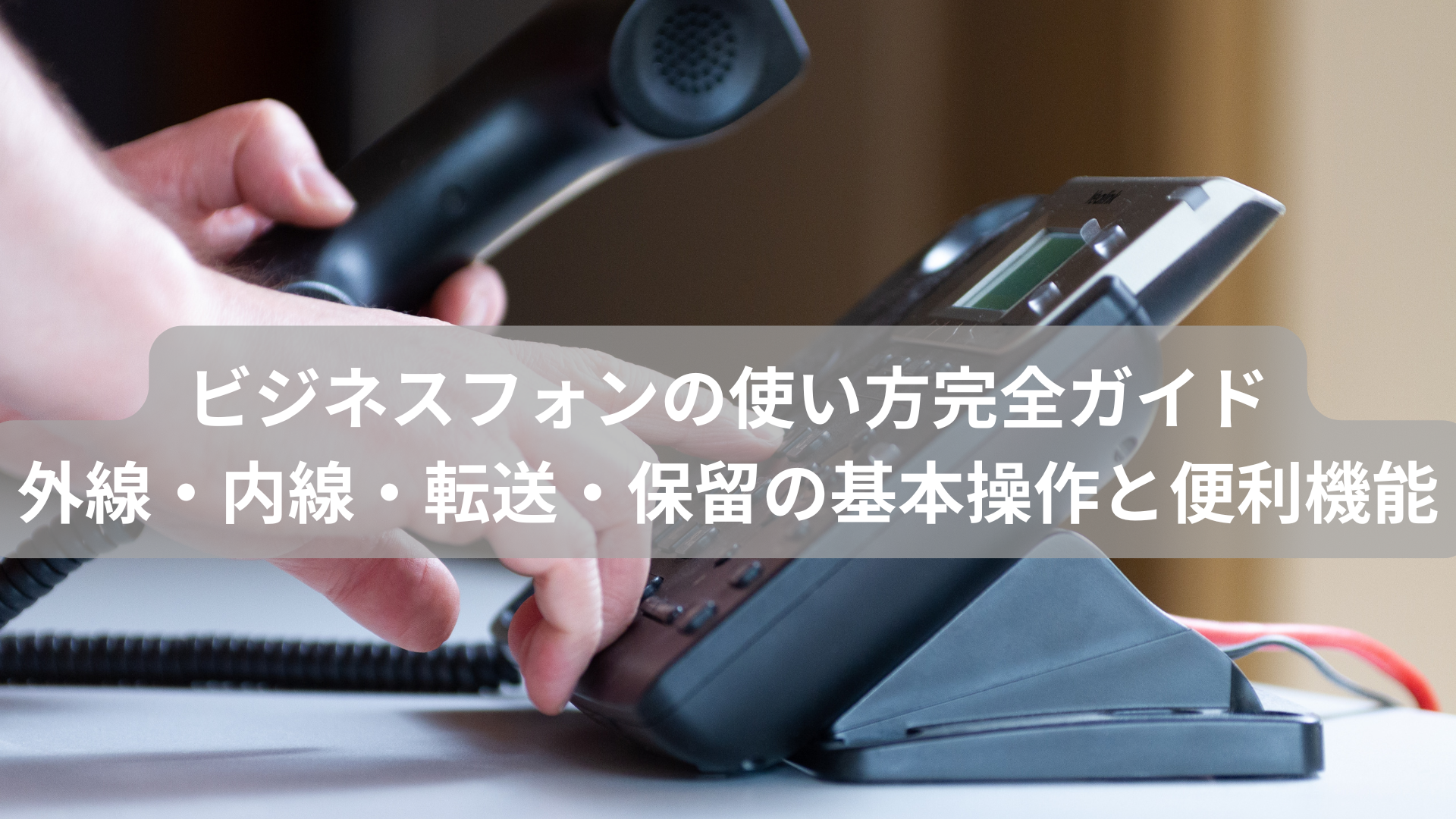
クラウド
この記事では、ビジネスフォンの基本的な機能である外線・内線・転送・保留の使い方から自動音声応答やボイスボット等の便利機能までビジネスフォンを触ったことが無い方でもわかりやすいように詳しく紹介しています。
2025-03-19
4min