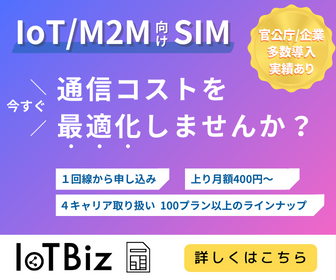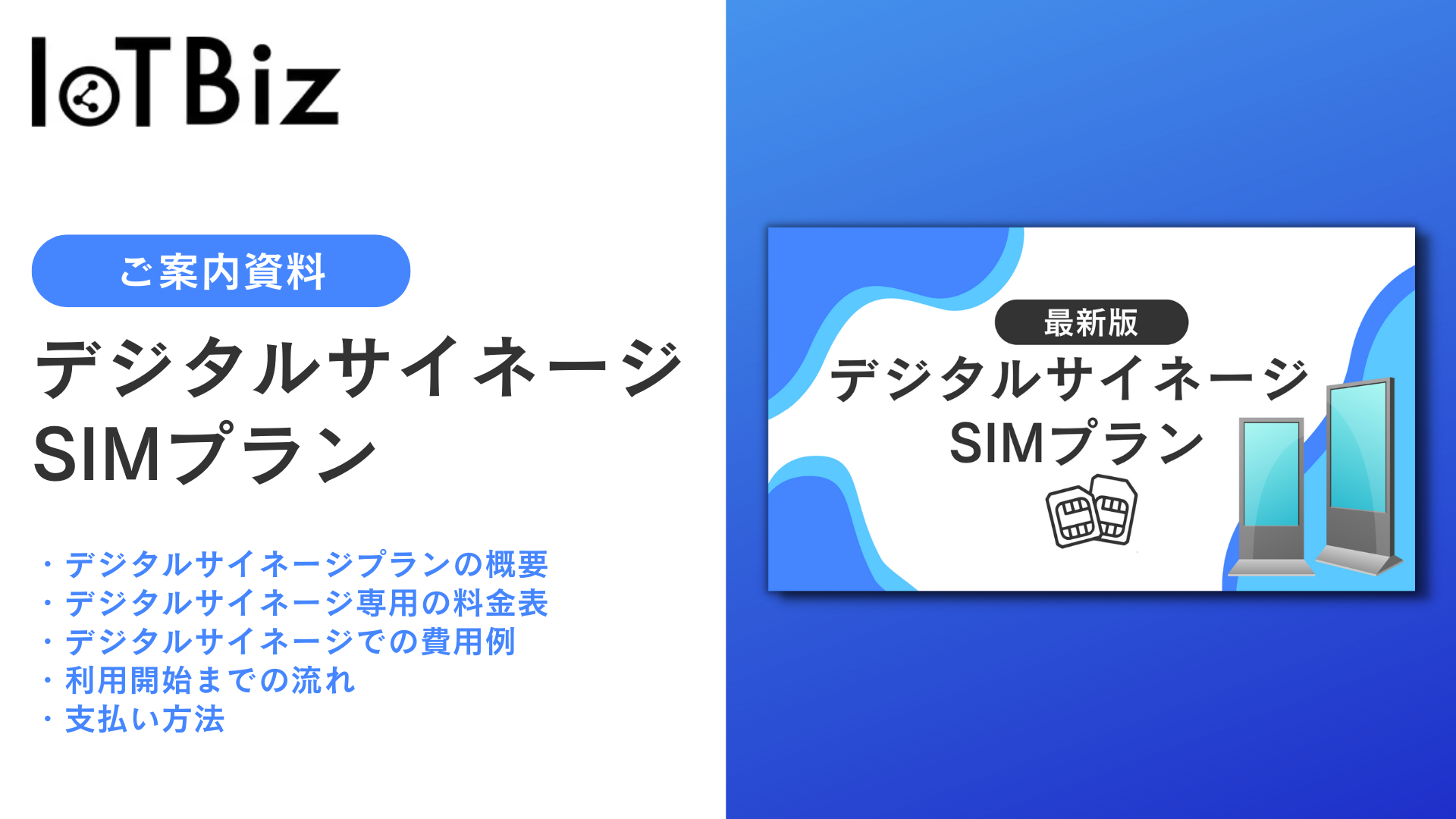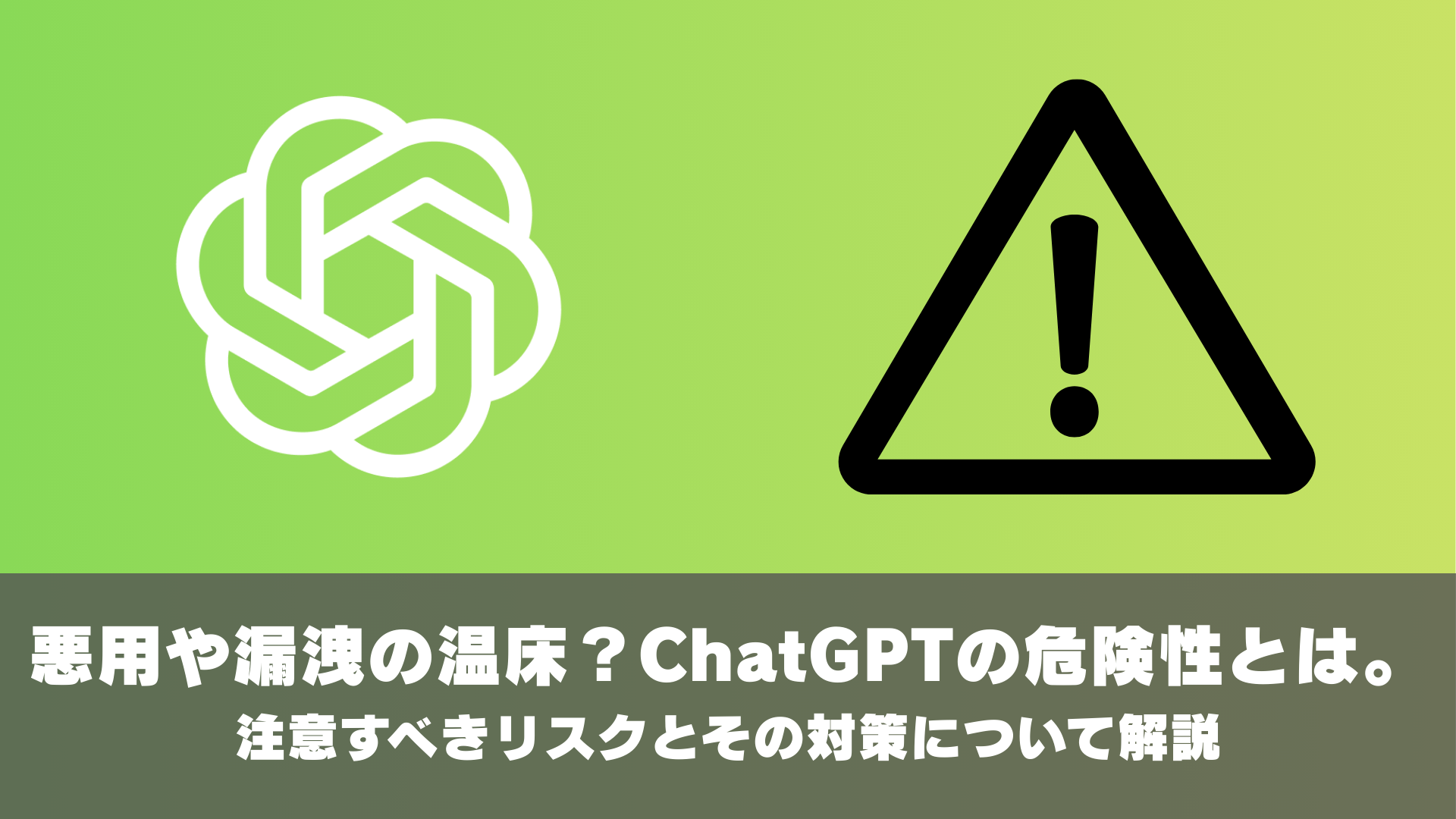nanoSIMとeSIMの違いとは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説
nanoSIMとeSIMの違いとは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説
SIM
2025-09-22
6min

スマートフォンやIoT機器に欠かせないSIMには、従来のnanoSIMと、新しい形式のeSIMがあります。どちらも通信契約に必要ですが、仕組みや使い勝手に大きな違いがあります。本記事では、法人・個人の利用者に向けて、それぞれの特徴を整理しながら、どちらを選ぶべきかを解説します。
目次
まずSIMカードの基本と役割を確認
現代の通信環境において、SIMカードは欠かせない存在です。
特に、nanoSIMとeSIMは、スマートフォンの通信機能を支える重要な要素となっています。これらのSIMカードが通信を行う上で必要識別情報を保持する役目を果たすことで、携帯会社からの認証を受けてデータ通信や音声通話を行うことを可能にし、私たちの生活を便利にしています。
どちらを選ぶべきかは、使用シーンやデバイスによって異なるため、これから解説する内容をしっかりと理解しておくことが大切です。
nanoSIMとeSIMどちらも使えるデュアルSIMと呼ばれる機種も一般的になってきています。
デュアルSIMについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
https://iot.dxhub.co.jp/articles/ux0q46jf5_av
nanoSIMとeSIMとは?基本の特徴を解説
nanoSIMは、従来のSIMカードの中で最も小型の物理カードで、一般的にスマートフォンに
挿入して使用します。別の回線を使用したい場合はSIMカードの差し替えが必要になります。
一方、eSIMは、デバイス内部に組み込まれた電子的なSIMで、物理的なカードを必要とせず、オンラインで契約情報を管理・更新できます。これにより、SIMカードの差し替えが不要になり、利便性が向上します。ただし利用は対応機種のみに限られ、自由に他端末に差し替えることはできません。
また、nanoSIMとeSIMは併用が可能です。
多くのスマートフォンは、nanoSIMスロットとeSIM機能の両方を搭載しています。
これにより、ユーザーは必要に応じて、物理的なカードとデジタルSIMを使い分けることができます。
例えば、メインのプランをnanoSIMで使用し、旅行用のプランをeSIMで管理することが可能です。
SIMカードの歴史
SIMカードは当初、大型の標準SIMしかありませんでした。その後、小型化が進み現在主流のnanoSIMが一般的になりました。そしてついに現在では内蔵型のeSIMの普及が進んでいます。
現在新たにiSIMと呼ばれるeSIMの進化系となるSIMカードの実用化も進んできています。
従来のeSIMは専用のモジュールを別で搭載していましたが、iSIMはデバイスのメインのチップに最初から内蔵されている点が主な違いです。
SIMカードの歴史とそれぞれの特徴を簡単にまとめた表は、こちらです。
| 種類 | サイズ(縦×横×厚さ) | 登場時期 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| フルサイズSIM(Standard SIM) | 85.6mm × 53.98mm × 0.76mm | 1990年代初頭 | クレジットカード大のサイズ。初期の携帯電話で利用。現在はほぼ使用されていない。 |
| Mini SIM | 25mm × 15mm × 0.76mm | 1996年頃 | 「標準SIM」とも呼ばれる。2000年代の多くの携帯電話で利用された。 |
| Micro SIM | 15mm × 12mm × 0.76mm | 2010年頃 | 初代 iPad や iPhone 4 で採用。Mini SIM より小型化し、省スペース設計に貢献。 |
| Nano SIM | 12.3mm × 8.8mm × 0.67mm | 2012年 | 現在主流のSIM。iPhone 5 以降や多くのAndroid端末で採用。小型で端末の設計自由度を高めた。 |
| eSIM | 端末内蔵チップ(物理カードなし) | 2016年以降(普及は2018年頃~) | 遠隔でプロファイルをダウンロード可能。物理カード不要で即日開通や複数回線の切替が容易。 |
| iSIM | SoC(プロセッサ)内蔵 | 2021年頃(商用展開は2023年以降) | 通信モデムやCPUと一体化されたSIM。省電力・省スペース化に優れ、IoT機器や次世代スマホでの活用が期待されている。 |
|
※登場時期は代表的な採用開始の目安。メーカーや国によって差があります。 関連記事: SIMカードとは?基本的な種類やサイズ、仕組み、選び方を解説 / SIMカードとeSIMの違いを徹底解説 |
|||
nanoSIMとは
まずは、nanoSIMの特徴やメリット・デメリットについて確認していきます。
nanoSIMの仕組み
nanoSIMは、現在もっとも広く使われている物理SIMカードです。SIMカードスロットに挿入することで通信事業者と認証され、モバイル通信が可能になります。サイズは従来のminiSIMやmicroSIMより小さく、スマートフォンやIoT機器に適した形状です。
SIMカードについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
SIMカードとは?基本的な種類やサイズ、仕組み、選び方を解説
nanoSIMのメリット
nanoSIMの3つのメリットを詳しく紹介していきます。
1.幅広い端末に対応
ほとんどのスマートフォンやタブレット、IoT機器で利用可能です。一部apple製品を除きほとんどの機器で使用できるため、eSIMに対応しているか分からない場合はnanoSIMを選んでおけば間違いありません。
2.乗り換えが容易
nanoSIMは、カードを抜き差しするだけで使用端末を変更できます。そのため、家族や会社で必要な時にだけSIMカードを挿入することで、契約する回線の数を節約することも可能です。また、複数キャリアの回線を使い分けることも容易です。
3.通信トラブル時の対応がしやすい
カード交換で復旧可能なため、複数枚保有していればすぐに取り替えられ法人利用にも安心です。また、海外出張などで急に回線が使えなくなった場合も現地でSIMカードを購入すればすぐに使用可能になるため、WiFi環境がないと設定できないeSIMよりも緊急時の信頼性は高いと言えます。
nanoSIMのデメリット
nanoSIMの2つのデメリットについて、紹介していきます。
1.紛失や破損のリスク
物理カードのため、取り扱いに注意が必要です。挿入の際に上の基盤部分を傷つけてしまうと故障してしまう可能性があります。また、長年使っていると劣化し、正しく使っていても交換が必要となる場合があります。
2.発行・配送の手間
SIMカードを発行し配送するのに時間がかかるため新規契約や再発行時に数日かかる場合があります。eSIMは最短10分で開通できるため、緊急を要する場合はeSIMに軍配が上がります。
eSIMとは
次に、eSIMについて詳しく解説していきます。
eSIMの仕組み
eSIMは、端末に内蔵された書き込み可能なSIMで、物理カードを必要としません。契約情報はプロファイルとしてダウンロードされ、QRコードや専用アプリを通じて即時利用できます。
具体的には、端末内にSIMカードが内蔵されていてオンラインで契約情報を書き込んで使用するイメージです。簡単に設定できて便利な半面、物理SIMと違って一度書き込むと他の端末に移し替えられない為、柔軟な運用は難しくなっています。
詳しくはこちらの記事をご確認ください
SIMカードとeSIMの違いは?それぞれの特徴やメリット・デメリット、注意点を解説
eSIMのメリット
1.即日開通可能
オンラインで契約から利用開始まで完結していて、最短10分程度での開通が可能です。好きなタイミングで開通できるため、必要になった時にすぐに回線を用意することができます。
2.物理カード不要
紛失や破損のリスクがなく、スマートな利用が可能です。SIMカードの差し替えの際のトラブルとしては、SIMピンの紛失や挿入時のSIMカードの初期不良等が挙げられます。eSIMであれば設定をするだけなので、これらの不意のトラブルに見舞われて大事な時に通信ができないといった事態を避けることができます。
3.複数プロファイルの管理
eSIMは、1台の端末で複数の通信事業者を切り替えて使用可能です。ただし、同時に有効にできるのは1回線だけなので電話番号を同時に10種類有効にするといった事はできませんので注意してください。
eSIM2種のデュアルSIMを搭載している機種もあり、その場合は同時に2回線まで有効にすることができます。
複数の回線の切り替えによって仕事や家庭での電話番号の使い分けや、時間帯によって繋がりやすいキャリアの使い分けが可能になり。通信の使い方の幅が大きく広がります。
eSIMのデメリット
1.対応端末が限られる
古い機種や一部のIoT機器では利用できません。日本での普及率も半数程度と言われています。また、世界全体でもまだまだ普及しきっていない為、場合によってはnanoSIMの方が役に立つ場面もあります。
2.トラブル時の切り替えが難しい
物理的な抜き差しができないため、不具合が起きた場合のサポート依存度が高くなります。eSIMの設定は少し複雑なため、慣れていない場合は設定に失敗してトラブルになってしまうケースがあります。
3.設定にWiFi回線が必要
eSIMのプロファイルを設定するのには、WiFi環境が必要になります。何も通信環境がない場所では開通できませんので、あらかじめ開通しておく必要があります。
ただし、最新の一部機種ではWiFiがない場所でも開通ができるようになっています。
nanoSIMとeSIMの主な違い
ここまで紹介してきたnanoSIMとeSIMについて、それぞれの違いについて分かりやすくまとめて紹介します。
1.サイズと物理的な有無
nanoSIMはカードとして実体がありますが、eSIMは端末内に組み込まれているため、物理的な差し替えは不要です。
2.利用開始までの手順
手続きのしやすさの点では、全てオンラインで完了するeSIMに軍配が上がります。ただし、どちらの場合でも本人確認情報等の登録は必要です。
- nanoSIM:SIMカードの発行・郵送を待ち、端末に挿入して設定
- eSIM:オンライン手続き後、QRコードやアプリで即時開通
3.対応端末の違い
nanoSIMはほぼ全端末で利用可能ですが、eSIMは最新のスマートフォンや一部のIoT機器に限られます。ただしeSIMの普及率は年々増加しています。
4.セキュリティや利便性の違い
セキュリティ面では、eSIMはデジタルで管理されるため、物理的なカードを紛失するリスクがありません。
また、eSIMはリモートでの管理が可能で、セキュリティが強化されています。
一方、nanoSIMは物理的なカードであるため、紛失や盗難のリスクがありますが、取り扱いが簡単で、特に技術に不安がある方には向いています。
nanoSIMとeSIMの違いについての詳細はコチラの記事もご覧ください。
SIMカードとeSIMの違いは?
どちらを選ぶべきか?利用シーン別のおすすめ
法人利用での選び方
法人契約では、運用管理やトラブル対応のしやすさが重視されます。端末の入れ替えや交換を頻繁に行う場合はnanoSIMが適しています。一方、IoT機器を大量に展開し、現地でのSIM交換を避けたい場合はeSIMが効率的です。
法人契約できるSIMカードをお探しの方は、こちらの記事もご覧ください。
法人契約で使えるデータSIMまとめ!おすすめの格安SIM12選を紹介
個人利用での選び方
スマートフォンの機種変更を頻繁に行う人や、海外渡航が多い人にはeSIMが便利です。一方で、家族や複数端末でSIMカードを共有したい人や、サポート体制を重視する人にはnanoSIMがおすすめです。
SIMカードの選び方やおすすめのプランについてはこちらの記事をご確認ください。
SIMフリーとは?格安SIMやスマホの違い・メリット・選び方・注意点をわかりやすく解説|IoTBiz
自分のデバイスを確認する手順
自分のデバイスがnanoSIMまたはeSIMに対応しているかを確認するには、以下の手順を参考にしてください。
・デバイスの設定メニューを開く
・「ネットワーク」または「SIMカード」セクションを選択
・対応するSIMカードの情報を確認する
・公式サイトや取扱説明書で詳細を確認する
eSIMへの乗り換えとMNPの利用方法
これからnanoSIMからeSIMに乗り換える方のために、MNPの使い方と、eSIMへの変更方法を紹介します。
MNP(モバイルナンバーポータビリティ)とはキャリアやSIMを変更する際に電話番号をそのまま引き継げるシステムのことです。
■ MNPを利用した乗り換え手続き
MNP(モバイルナンバーポータビリティ)を利用することで、電話番号を変えずにキャリアを乗り換えることができます。
ここでは、MNPの流れと注意点、nanoSIMからeSIMへの変換手順を解説します。
□ MNPの流れと注意点
MNPを利用する際の基本的な流れは以下の通りです。
1.現在のキャリアからMNP予約番号を取得する
2.新しいキャリアで契約手続きを行う
3.SIMカードを受け取り、デバイスに挿入する
4.設定を行い、通信が可能か確認する
注意点として、MNP予約番号には有効期限があるため、早めに手続きを行うことが重要です。また、契約内容によっては、解約手数料が発生する場合があります。
□ nanoSIMからeSIMへの変換手順
nanoSIMからeSIMへの変換は、以下の手順で行います。
1.現在のキャリアに連絡し、eSIMへの変更を依頼する
2.eSIMのQRコードを受け取る
3.デバイスの設定メニューからeSIMを追加する
4.QRコードをスキャンし、プロファイルをダウンロードする
5.設定が完了したら、通信が可能か確認する
まとめ
nanoSIMは物理的な互換性と安定性が強みであり、eSIMは利便性と柔軟性が魅力です。法人利用では運用形態や導入規模に応じて選択が必要であり、個人利用ではライフスタイルに合わせた選び方が重要です。
IoT Biz ではSIMに関する比較記事を豊富に掲載しています。導入検討の際には以下もご参考ください。
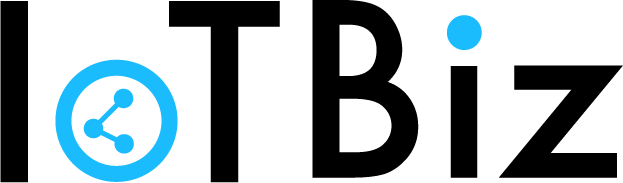
IoTBiz編集部
2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。
関連記事
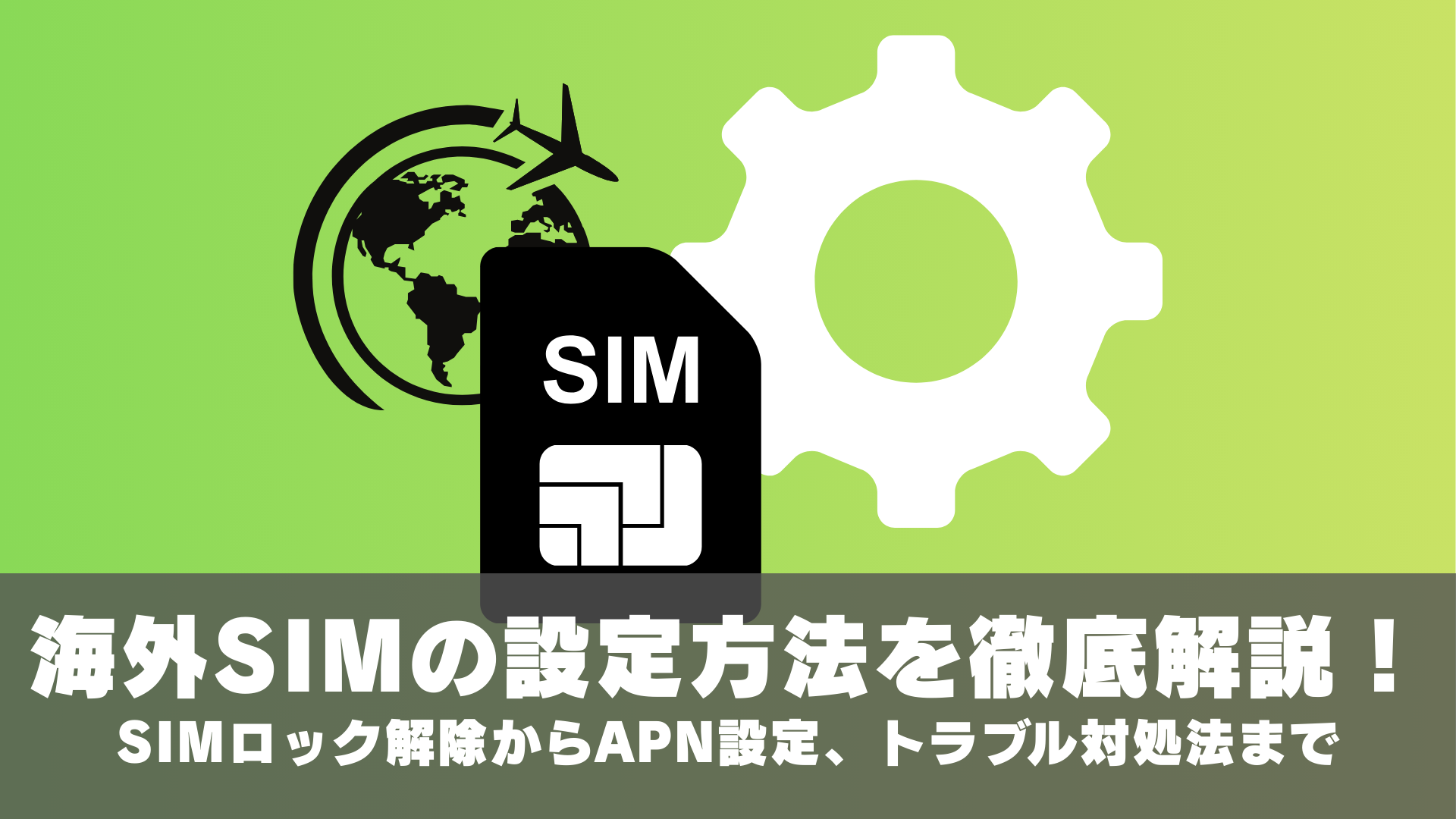
スマホ
SIM
海外SIMの設定方法を初心者向けに徹底解説。全体フローから、iPhone・AndroidのAPN設定方法、eSIMの使い方、繋がらない時のトラブル対処法まで、海外旅行や出張で役立つ情報を2025年最新版でお届けします。
2025-12-22
11min

SIM
海外旅行でスマホを使う際、SIMとWiFiはどっちを選ぶべきか迷う方へ。本記事では、海外レンタルWiFi・海外SIMカード・eSIMのメリット・デメリットや料金を徹底比較し、利用シーン別におすすめの通信手段を解説します。
2025-12-22
8min
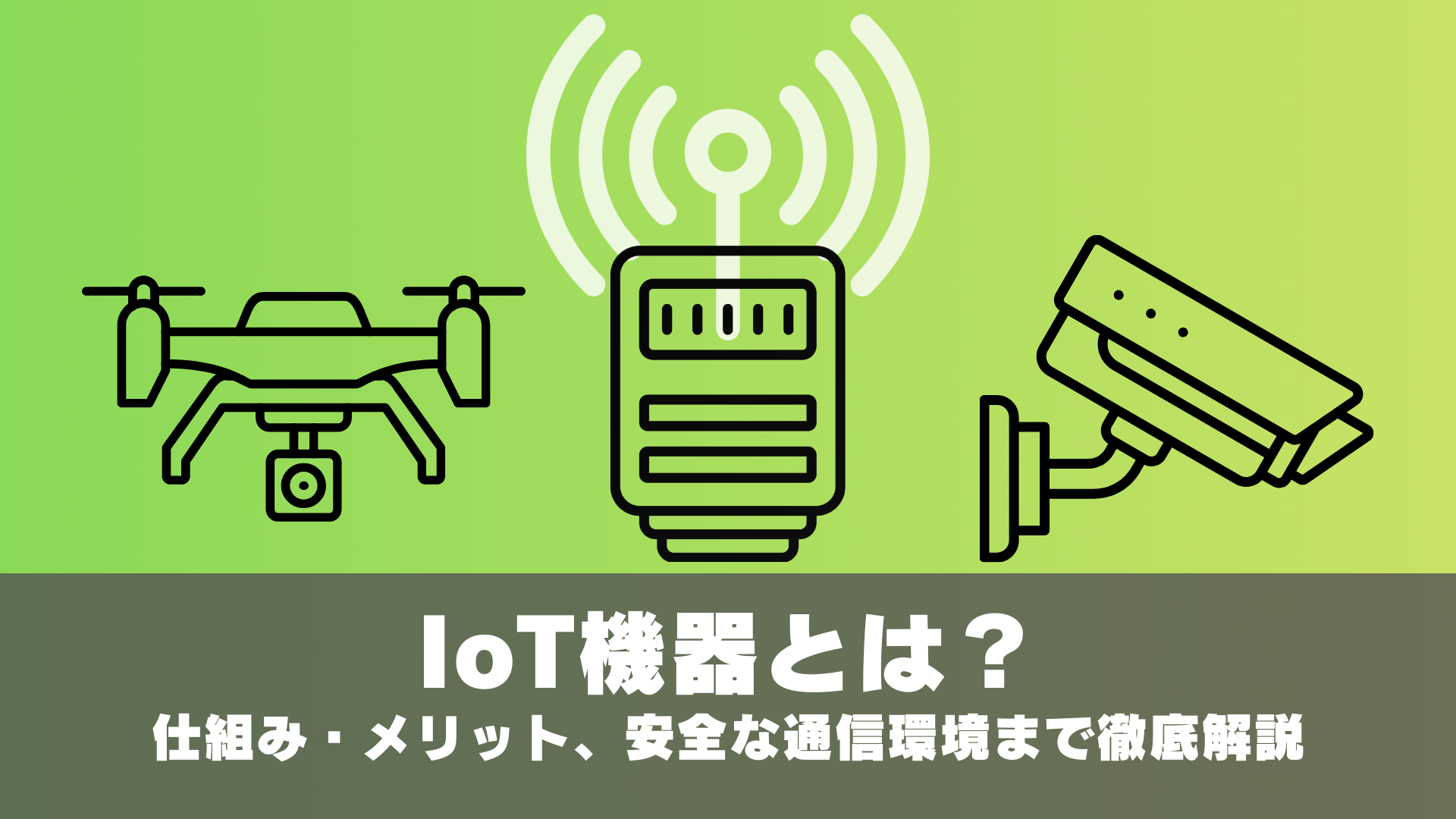
IoT
SIM
本記事では、「IoT機器とは何か」という基本定義から、ビジネスにおける具体的な活用事例、導入メリット、そしてIoT機器を安心・安全に運用するための通信環境の選び方までを、詳しく解説します。
2025-12-09
7min