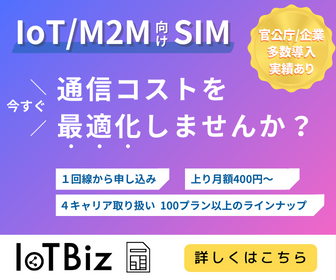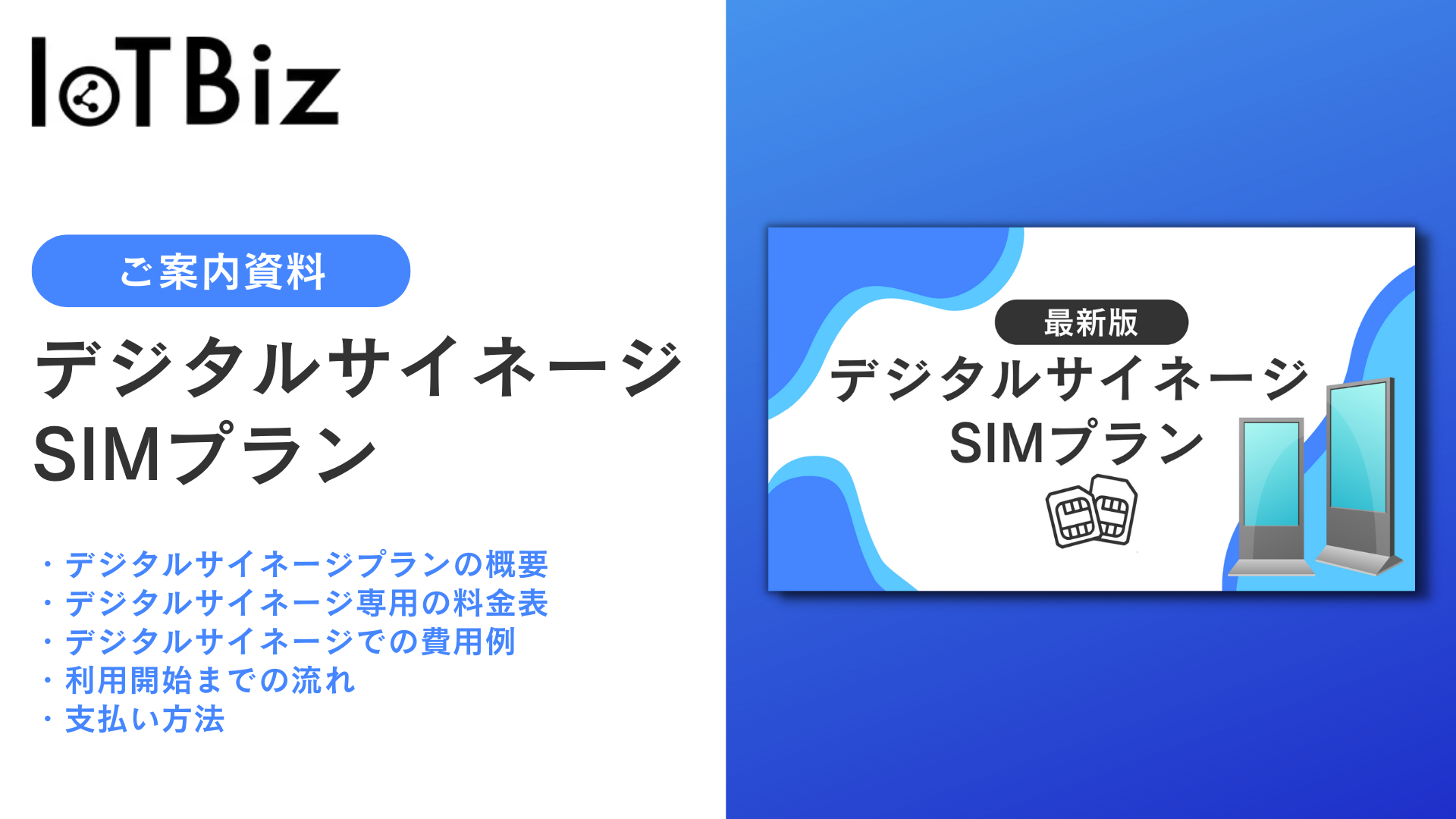建設DXとは?メリットや成功事例を紹介
建設DXとは?メリットや成功事例を紹介

デジタル・テクノロジーの力を活用して産業構造を変化させることを「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」と呼んでおり、多くの業界で導入が進んでいます。 全ての業種で「DX」が求められていることを前提として、業界の持つ特有の課題から「建設業のDX推進」は業界内外からも注目を集めているのです。 しかし、実際にデジタル・テクノロジーの力を活用してどのように業界構造を変えていくのかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか? この記事では、建設業が抱える課題から建設DXのメリット、建設業においてDXを取り入れた事例などを建設業にも適用された時間外労働の上限規制や、公共事業でのBIM/CIM原則適用・遠隔臨場などの最新動向も交えて解説します。
目次
建設業が抱える課題
数多くある業種・業態の中でも「建設業」が注目される背景には、業界特有の課題があります。
DXの導入が早急に求められる建設業には、どのような課題があるのかを見ていきましょう。
「働き方改革関連法」が2024年4月から適用される
日本では「働き方改革関連法」によって、企業は1日8時間、週40時間の法定労働時間を遵守する必要があり、法定労働時間を超えて働く場合には36協定の締結が必要です。
36協定を締結した場合でも残業時間には上限があり、最大でも月45時間、年360時間以内と定められています。
しかし、「医師」「自動車運転業務」「建設業」は特例措置として労働時間の上限規制に一定期間の猶予が与えられていました。
2024年4月からは特例措置が撤廃され、「建設業」でも災害復旧など一部例外を除き、建設業にも一般則どおりの上限(例:月45時間・年360時間等)が適用されています。
そのため、労働時間の上限規制を気にして企業が労働を指示する必要があり、企業は限られた人員・時間の中での業務効率化が一層求められています。
高齢化・人材不足
一般社団法人日本建設業連合会が発表している「建設業デジタルハンドブック」に記載されている建設業就業者数は1997年の685万人をピークに減少し、2024年は477万人(ピーク比69.6%)で内建設技能者は303万人(ピーク比65.3%)です。
また、「建設業就業者の年齢別構成比の推移」を見ると、55歳以上の建設業就業者の割合が2005年には29.4%であったのに対し2024年では36.7%まで増加、29歳以下の建設業就業者は2005年には19.7%だったのに対して、2024年は11.7%まで減少しました。人材の高齢化は日本全体の問題となっていますが、全業種での55歳以上の就業者は32.4%、29歳以下の就業者は16.9%であるため、他業種と比べてもより就業者の高齢化が進んでいる状況です。
日本全体で少子高齢化も進み、人材確保の難易度が増加していく中で、DXを活用した業務効率化が喫緊で求められています。
(参考)建設業デジタルハンドブック
低い労働生産性
システムツールが発展している現在においても、建設業は図面・報告書が未だ紙ベースでやり取りされるなどアナログな要素が強いです。現場から帰った後も事務所内で報告書を制作する必要があったり、変更が一個入るだけで紙ベースで作成している大半を再作成する必要があるなど、効率的に作業できる環境とは言えません。
国交省はBIM/CIMの原則適用や遠隔臨場の実施要領整備で、測量〜検査までの3次元データ・遠隔確認を標準化し、生産性の底上げを図っています。
(参考)令和5年度BIM/CIM原則適用について
危険作業のリスク
高所作業など働く上で危険を伴うことから、全ての業種の中でも労働災害が多いことも課題のひとつです。
2023年の死亡者数は全産業で755人、うち建設業が223人で最多(前年比20.6%減)です。型別では「墜落・転落」が最多でした。年々死亡数は減ってきていますが、依然として業種別では最多の件数となっています。
若い世代も近年は、就職も売り手市場であることから、危険作業が伴う建設業は敬遠されてしまいます。
危険な作業を減らして、現場の安全性を向上させることにDXが求められているのです。
技術継承問題
建設業の高齢化が着実に進んでいる中で、長年培ってきた技術を持った人材が高齢に伴って技術継承ができないままに引退するケースも問題となっています。継承先となるはずの若手・中間層が減少しており、企業資産であるはずの熟練技術が失われていくことは企業目線でも避けたいでしょう。
近年は、熟練の技術を持った職人の動きをAIが映像解析して、動きを再現できるように標準化する新しい技術継承の仕組みが実現に向かっています。このような観点からも、DXの導入は早急に求められるのです。
建設DXとは
AI・ICTなどの最新技術を活用して、建設業が抱える「人材不足」「作業効率化」「技術継承」などの課題を解決することを「建設DX」と呼んでいます。しかし、現実として建設業界の多くは「勤怠管理」「図面管理」などに独自システムが定着しており、一概に効率的とは言えないのが現状です。
DX化して業務を効率化する際は、業務の始まりから終わりまで、包括的に業務プロセスを見直すことが重要です。工程ごとに導入したシステムが連携できていなければデジタル化をしたとしても業務の効率化には繋がりにくいです。
次に、建設業のDX化に向けた政府の動きについて押さえておきましょう。
内閣府が定義した「Society 5.0」とは?
内閣府が定義した「日本が目指す未来社会の姿」として提唱されたものが「Society 5.0」です。
「狩猟社会」(Society 1.0)「農耕社会」(Society 2.0)「工業社会」(Society 3.0)「情報社会」(Society 4.0)に続く社会であり、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合したシステムによって、経済発展・社会的課題解決を両立する社会」と定義されています。
「インターネットがあらゆるモノを繋げる」ことで、新たな価値を生み出して、「AI」「ロボット」などの最新技術が社会課題を解決する鍵になるとしています。
建設業においても、デジタルツールを活用した業界改革が必要です。
国土交通省が主導で行う「i-Construction」とは?
「i-Construction」とは、「測量」「設計」「検査」「維持管理」に至る全ての事業プロセスでICTを導入することで、建設生産システム全体の生産性向上を目指します。
さらに「i-Construction」を理解する上で必要な3つのキーワードを解説します。
(1)CIM
CIMとは、3Dモデル・仕様情報を一貫して管理するシステムのこと。
CIMを導入して設計段階から3Dモデルで議論することで、実際に着工するまで気づかなかった課題や潜在的な問題を鮮明に顕在化できるようになり、工事の手戻りを防ぎます。
(2)ドローン
測量する際にドローンを用いることで、数百万地点の測量を約15分で完了します。
さらに測量データを3Dデータで作成することが可能となり、施工時に必要な土の量を自動で計算するなどの作業自動化にも貢献するのです。
(3)ICT建機
建機の操縦は長年の経験を必要とする難易度の高い業務であることから、ある一定の経験のあるスタッフに依存してしまう問題も引き起こしていました。自動制御機能を搭載した最新のICT建機を導入することで、経験の浅い操縦士でもアシストを受けながら施工が行えるのです。
「施工の正確性」も担保される他、「安全性向上」も見込まれます。
これら3つの特徴をまとめた表が、以下になります。
| カテゴリ | 主な目的 | 期待効果 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| BIM/CIM | 3Dモデルで設計~施工・検査を連携 | 干渉削減・合意形成の迅速化・出来形精度向上 | モデル作成体制・標準化、発注要件との整合が必要 |
| 遠隔臨場 | 段階確認・立会・材料確認の非対面化 | 移動・待機の削減、迅速な意思決定、記録の一元化 | 通信品質、撮影機器、記録保全の運用設計が必要 |
| ICT建機 | 自動制御・出来形連携による施工高度化 | 省人化・安全性向上・品質の平準化 | 初期投資とオペレータ教育、データ連携の設計 |
建設DXが注目される背景
数多くの業種・業態でも「DX導入」が求められている中で、なぜ「建設業」におけるDX導入が注目を集めているのでしょうか?
具体的な背景を押さえておきましょう。
ビジネスのオンライン化
2019年から世界中に拡大した感染症「新型コロナウイルス」の影響で、日本全体でビジネスのオンライン化が急速に進行しました。
建設現場で実際の建造物を確認しながら打ち合わせするスタイルが当たり前だった建設業界では、オンライン化する顧客にどう対応するべきか、社員間のコミュニケーションをどのような形で維持するべきかが大きな課題となり、その環境でどうDXを進めるかが注目されています。
「2025年の壁」
「2025年の壁」とは、2018年に経済産業省がまとめたレポートで提示された問題です。
多くの企業でシステム老朽化が進んでいることから、この状態が継続されると、既存システムの維持管理費がIT予算の90%以上になり、新しいシステムへの投資が行われないことを危惧しています。
また、2025年には専門的知識を有しているIT要員不足が慢性的に発生して、サイバーセキュリティに関連する事故・災害トラブルのリスクも高まると予測されているのです。
老朽化が進む既存システムの依存から脱却できなければ、2025年以降、日本経済は「システム障害」「データ損失」によって年間最大12兆円の経済損失が生まれる可能性があると経済産業省は警告しています。
このような背景から、建設業のDXは注目を集めているのです。
建設DXのメリット
老朽化する既存システムを維持することで莫大な経済損失が生まれる以上、建設業のDX推進は今後も進んでいくことが予測されています。
建設DXを推し進めることで、得られるメリットを押さえておきましょう。
業務効率化の促進
具体例として、今まで紙ベースの平面図面を描いて顧客と打ち合わせしていたものを、3Dデータなどを用いて立体的な図面を描くことで、現場での打ち合わせ等をオンラインで進めることが可能です。
オフラインで面談する上で必要な打ち合わせ会場までの移動時間を省けると、他の作業に当てられる時間が増えるため、効率的に仕事を進められます。
省人化を進められる
具体例として、今まで建設機械に人が乗り込んで作業していたものを、遠隔操作する形にシフトした場合、安全監視機器(監視AI等)の導入で危険が発生した際に素早く対応が可能になるになります。
このようなことから、省人化が進められる他、採用難易度が高い専門技術を持つ人材も不要になるでしょう。
また、遠隔操作によって無人で建設機械を動かすことが可能になり、作業者の安全性を高めることにも繋がります。
技術継承をスムーズに進められる
長年経験を積んで培ってきた熟練の技術を継承する若い世代が減少していますが、デジタル技術を活用して記録することもDXで実現可能です。
貴重な熟練の経験値をシステムに登録することで、若い世代がいつでも簡単に確認して、自分のスキルアップに生かせます。今までは仕事の業務時間内に直接学ぶ必要があったスキルも、システムの中に記録することでPC・タブレットなどを活用して「いつでも」「どこでも」学べる点も大きなメリットです。
建設DXの成功事例3選
一概に「建設DXを推進するべき」と表現しても、具体的に企業がどのような形で建設DXを成功させているのか知りたい方も多いのではないでしょうか?
最後に、建設DXの成功事例を紹介します。
「清水建設株式会社」の事例
「ものづくりの心を持ったデジタルゼネコン」を謳っている清水建設は、構造・性能をシミュレートするコンピュテーショナルデザインを設計段階から活用し、BIMデータを連携させながら、施工現場では「ロボット」「3Dプリンタ」なども活用しています。
そのほかにも、以下についても積極的に取り入れているのです。
・AR技術を活用した施工管理の開発/実用化
・3Dプリンタでコンクリート柱を構築
・自律型溶接ロボットの活用
独自開発した建物運用デジタルプラットフォーム「DX-Core」を活用して、「エレベーター」「監視カメラ」などの建設設備・Iotデバイスと連携して、運用管理の効率化、利用者の利便性・安全性の向上にも貢献しています。
(参考)https://www.shimz.co.jp/engineering/solution/dxcore.html?utm
「ダイダン株式会社」の事例
「オンライン会議システム」「CADシステム」等を活用して、離れた場所からリモートで現場をサポートする体制をいち早く構築しました。
その他、クラウドを活用したビル管理制御システム「REMOVIS」を開発して、監視センターから顧客の設備運用・維持管理をサポートするサービスを提供し、少人数での設備管理を推し進めています。
(参考)クラウド型自動制御システム リモビス(REMOVIS) | ダイダン株式会社
「大成建設株式会社」の事例
多数の実証実験をソフトバンクと提携して行っているのが「大成建設」です。
具体例として、5G通信を活用した建設機械の無人化事象実験では、大成建設が開発したロボットシステム「T-iROBO」を使って、5Gによる超高速通信で遠隔操作・自律制御のための信号伝送を行いました。
また、「ガスセンサー」「環境センサー」などを用いて温度や二酸化酸素などをリアルタイムで監視して、危険値が検出された場合に作業員へアラートを送信する仕組みも検証して、実用化を進めているのです。
2023年には、土砂山を検出して自動で土砂の押し出し・敷均しを可能にする自立制御型ブルドーザーの開発に成功しています。
(参考)土砂山を検出し押土経路を自ら決定する自律制御型ブルドーザを開発 | 大成建設株式会社
東京都下水道局:ドローン点検で高所・粉じん環境への入炉を回避
汚泥焼却炉内部の点検をドローンで外部から遠隔操作することで内部へ作業員が入っての点検作業が不要になりました。
これにより、作業員が危険な場所に立ち入る必要がなくなり事故の危険がなくなった上、点検時間が短縮された為、焼却炉の稼働時間の増加しました。
https://digi-acad.metro.tokyo.lg.jp/contents/001-00068.html?utm
まとめ
建設業が抱える特殊な事情と問題点、建設DXを導入するメリットと大手企業が推し進める建設DXの成功事例などを深掘りして解説してきました。
アナログ業務が多く、危険・きつい・汚いの3Kイメージが強い建設業の仕事がDXを活用することで大きく変化しようとしています。DXを導入することでどのような変化が起きるのかを理解した上で、DXを概念レベルではなく実例を交えながら理解を深めることが大切です。
建設DXについてより深く知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【事例でわかる!】建設DXのメリットと課題を徹底解説!
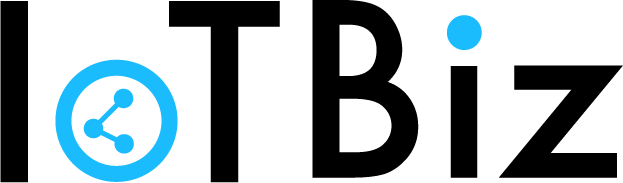
IoTBiz編集部
2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。
関連記事

カメラ
AI
AI防犯カメラとは、AIを搭載し映像の自動解析が可能な防犯カメラです。本記事では、仕組みや従来カメラとの違い、メリット・デメリット、導入費用、活用事例、選び方まで詳しく解説します。
2026-01-21
8min

AI
Claude Codeの料金プランを徹底解説。Proプラン月額20ドルからMax 20x月額200ドルまで、サブスクリプションとAPI従量課金の違い、利用制限、導入方法までを詳しく紹介します
2026-01-14
8min
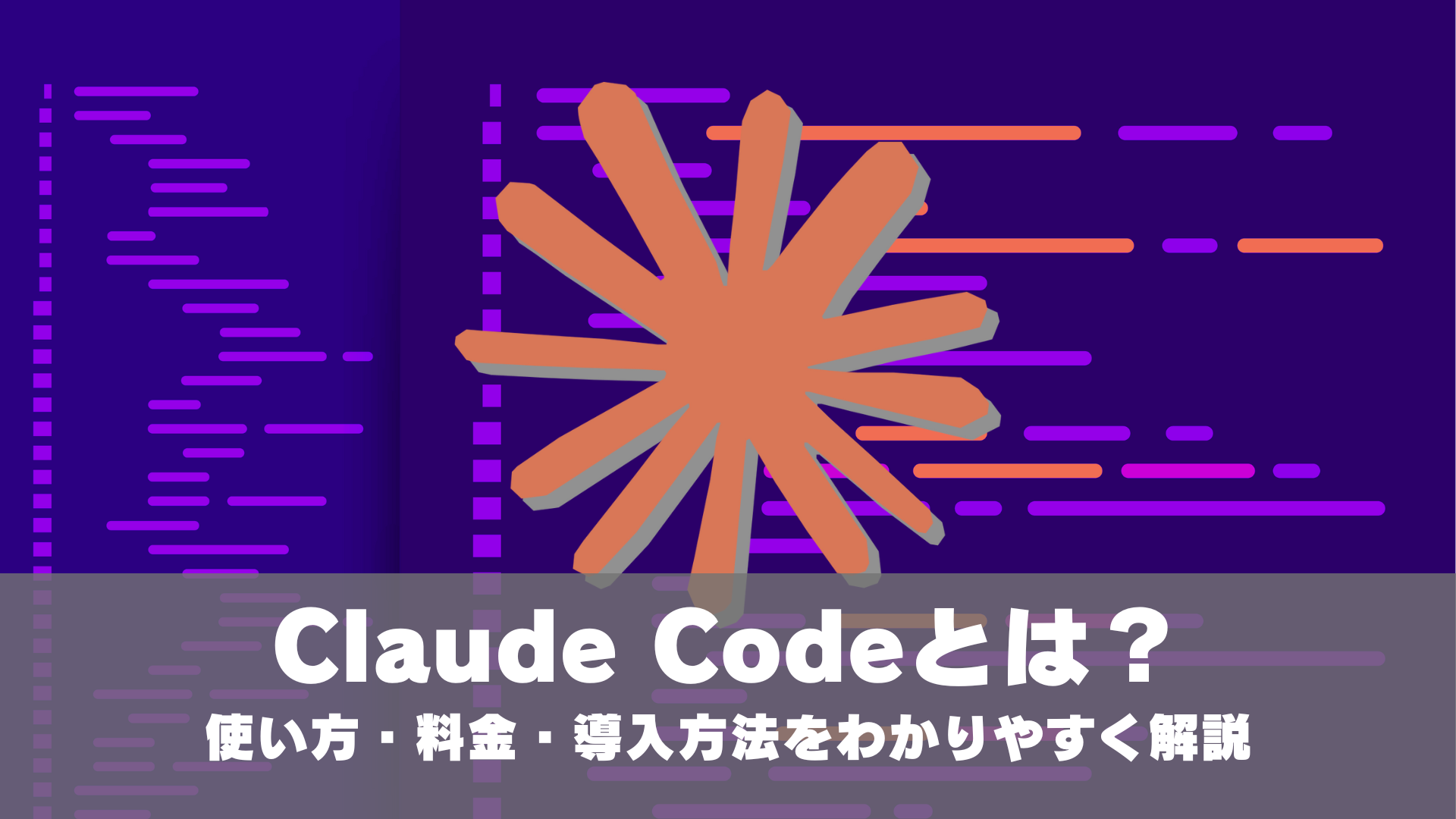
AI
Claude Codeとは、Anthropic社が提供するAIコーディング支援ツールです。本記事では、Claude Codeの機能や特徴、料金プラン、導入方法、使い方、活用事例までわかりやすく解説します。開発効率を向上させたい方は必見です。
2026-01-20
8min