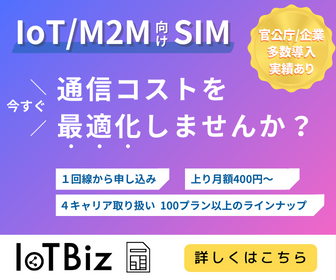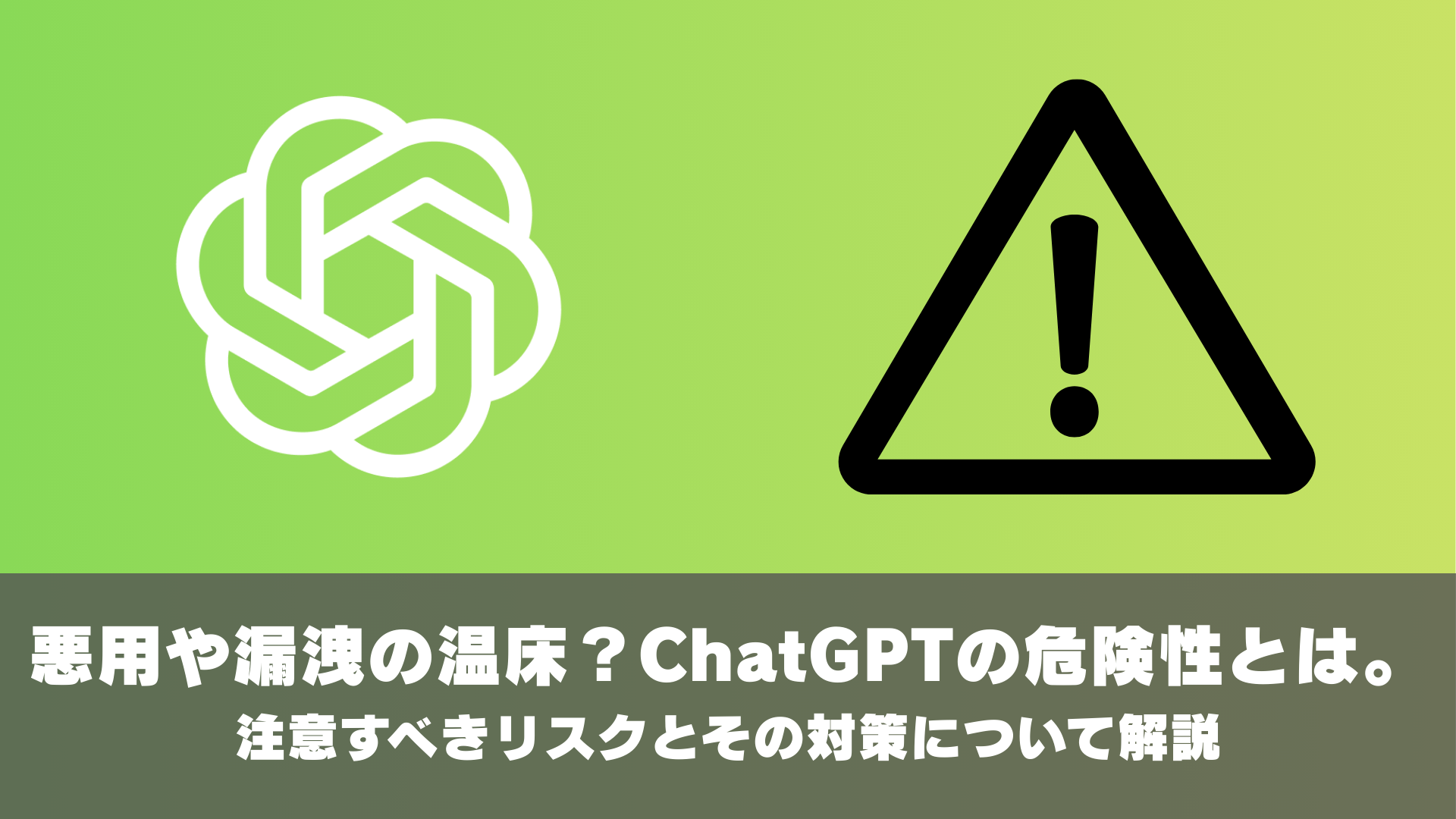スマートグリッドとは?メリット・デメリットや具体例を詳しく解説
スマートグリッドとは?メリット・デメリットや具体例を詳しく解説
スマート〇〇
2025-08-26
6min

スマートグリッドとは、電力効率を高める次世代型の送電網です。本記事では、スマートグリッドの仕組みや、メリット・デメリット、具体的な導入例を詳しく解説します。合わせてHEMSやスマートメーターといった関連語句も解説しています。
目次
スマートグリッドとは?
スマートグリッドとは、IT(通信)技術を駆使して、電力の流れを供給側と需要側が相互に制御できる送電網システムのことを指します。従来の電力網は一方通行であり、発電所から消費者へ電力を供給するだけのものでした。しかし、スマートグリッドでは、双方向のコミュニケーションが可能となり、消費者側からの情報もリアルタイムで収集し、分析することができます。これにより、電力の使用状況や需要の変動を正確に把握し、最適な供給を行うことができるのです。
このシステムは、電力の安定供給を目指すだけでなく、エネルギーの効率化やコスト削減、さらには環境負荷の軽減にも寄与します。例えば、再生可能エネルギーの利用が増える中で、その不安定な供給を補うための調整機能もスマートグリッドには含まれています。また、停電や故障が発生した際にも迅速に対応し、被害を最小限に抑えることができるのも特徴です。このようなシステムは、時間によって発電量が変動する太陽光発電や風力発電の普及によって需要が高まっています。
スマートグリッドの仕組み
スマートグリッドの基本的な仕組みは、電力網にセンサー、通信技術、データ分析ツールを組み合わせることによって成り立っています。
これにより、電力の供給側と需要側の情報をリアルタイムで収集し、効率的な管理を行います。具体的には、各家庭や企業に設置されたスマートメーターが重要な役割を果たします。このスマートメーターは、電力の使用状況を細かく計測し、その情報を中央システムに送信します。
中央システムでは、収集されたデータをもとに電力の需要予測を行い、供給側に指示を出します。例えば、需要が高まる時間帯には発電所の稼働を増やし、逆に需要が低い時間帯には発電を抑えるなどの調整が行われます。また、再生可能エネルギーの供給が不安定な場合でも、蓄電池や他の発電源を活用することで安定した供給を維持します。
さらに、スマートグリッドは異常検知や故障予測にも優れています。センサーが異常を検知すると、即座にその情報が中央システムに伝達され、迅速な対応が可能となります。このように、スマートグリッドは高度な技術を駆使して電力の供給と需要を最適化し、持続可能なエネルギー社会の実現を目指しています。
日本での導入状況
日本でのスマートメーターの普及率は2024年3月時点で85%に達し、2030年の政府目標に順調に近づいています。一方でスマートグリッドの普及率は40%程度にとどまっています。これは、電力供給側のシステムの更新がまだ間に合っていないことを示しています。
スマートメーター
スマートメーターとは、電力をデジタルで計れる電力計を指します。スマートメーターは電力消費状況を送信でき、電力の効率供給に貢献する他、検針に検査員が回る必要がないため、省人化とコストカットにもなります。利用する電力量のコントロールもできるため、利用者にとっても導入のメリットがあります。
スマートメーターについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
スマートメーターとは?特徴やメリット・デメリット、仕組み、見方を解説|IoTBiz
HEMS(Home Energy Management System)
HEMSとは、Home Energy Management System(ホームエネルギーマネジメントシステム)の略称で、家庭内のエネルギーを管理、制御するシステムを指します。具体的にはスマートメーターに接続されたHEMSコントローラーに各種の家電を接続します。家電の電力消費をコントロールすることで省エネ効果が期待されています。政府は、地球温暖化対策として2030年までの普及を目指しています。
電力制御だけでなく、暮らしが便利になる遠隔制御、音声認識、自動制御といった要素も包括した概念としてスマートホームがあります。
スマートホームについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
スマートホームとは?特徴やできること、メリット・デメリットをわかりやすく簡単に解説
BEMS(Building and Energy Management System)
BEMSとはビルエネルギーマネジメントシステム(Building and Energy Management System)の略称で、ITを利用してビル内の電力利用を最適化するシステムを指します。
具体的には、建物内のエネルギーの利用状況を予測し、最適な運転制御を行うシステムです。人感センサーでビル内の人の動きを確認し、温度計で温度を確認することで、冷房や証明を無駄なく使用することができるようになります。
BEMSの運用には、センサー、制御装置、中央監視装置といった機器の導入が必要となります。長期的には効率的になる一方で導入時には一定のコストがかかる点には注意が必要です。
FEMS(Factory Energy Management System)
FEMSとは、工場エネルギーマネジメントシステム(Factory Energy Management System)の略称で工場の電力消費をを分析・管理し、工場の省エネ化を実現するシステムです。
各工程の電力消費量を管理することで、電力消費を最適化できる他、各商品1つあたりの電力消費量や部署毎の電力消費量が可視化されることで、コスト計算が可能になり、電力消費量の変動から工場内の異変を察知することが可能になります。
CEMS(Cluster/Community Energy Management System)
CEMSは地域エネルギーマネジメントシステム(Cluster/Community Energy Management System)の略称で、これまで紹介したHEMS、BEMS、FEMSを統合し、IT技術を活用して地域全体の電力を管理し最適化するシステムを指します。従来の電力網との違いは、太陽光発電や蓄電池、電気自動車などの分散型エネルギーを組み合わせ、地域全体で効率的にエネルギーを管理する点です。具体的には、余剰電力を充電に回す、再生エネルギーを地産地消してロスを減らすといった方法で電力消費を効率化します。また、災害時の電力制御も容易になることから災害時の強靭性も高められます。
CEMSやスマートグリッドはスマートシティの実現のために欠かせない要素の1つとされます。スマートシティとは、IoTやAI、ビッグデータを活用し、人や企業の利便性や快適性がより向上し、地球環境への配慮を含めた持続可能な未来都市のことをいいます。
スマートシティについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
スマートシティ(Smart City)とは?定義や課題、日本と海外の事例を紹介
スマートグリッドのメリット
ここからはスマートグリッドの3つのメリットについて詳しく見ていきます。
電力量がリアルタイムでわかる
スマートグリッドを導入すると電力量を簡単に確認できるようになります。電力を効率的に使用できる他、検針の必要がなくなります。利用者目線では、いつでもスマホから電力量を確認でき、リアルタイムで把握できることから、家電のつけっぱなしといった異常に簡単に気づけるようになります。これを活用して、高齢者の生存確認に活用されている事例もあります。電力消費が急激に変動した家庭に見回りに行くことで、全ての家庭に見回りに行く場合に比べて少ない労力で高い効果を発揮できます。
データによる効率的な電力供給
発電量や需要のデータから、最適な発電計画を立てることができます。これにより、電力の輸送経路を最適化し、遠方の発電所からの送電による電力ロスを最小限に抑えることができます。
また、本来は無駄になるはずの余剰電力をバッテリーの充電に活用するといったことも可能になります。緊急性の低い充電のようなものを電力消費が少ない時間帯に行うことで、ピークタイムの発電所の負荷を軽減できます。
他にも、家庭やビル内で使用されていない部屋の電気やクーラーを停止する事による節電もスマートグリッドのメリットの1つです。
災害時のリスク軽減
スマートグリッドは、災害時の電力網の復旧にも秀でています。まず、一部の発電所が故障した場合でもすぐに非常用の電源に切り替え発電網を維持することができます。電力が不足している場合にも残存する太陽光発電や蓄電池から病院や警察といった重要施設に優先的に送電するといった柔軟な対応が可能であり、災害時の混乱を最小限に抑えることができます。
スマートグリッドのデメリット
ここからはスマートグリッドの2つのデメリットについて詳しく見ていきます。
導入と維持にコストがかかる
スマートグリッドの導入には多額の資金と地域全体での設置作業が必要となります。
特に各家庭にスマートメーターを設置する必要があり、電力会社が負担して取り替えなくてはいけません。スマートメーターの設置には多額の費用がかかるため、すぐに全てのメーターを取り替えるのは難しいという現実があります。
また、HEMSやBEMSといった管理システムは利用者が負担して設置する必要があるため、より導入のハードルは高まっています。
セキュリティ上の危険がある
スマートグリッドの制御装置が乗っ取られてしまえば、電力網が麻痺してしまう危険性があります。従来の制御機器に比べて、IT技術を活用する分通信経路が増大し、その分侵入されるリスクも高まっているというわけです。
また、家庭の電力の使用量に関するデータが漏洩してしまえば生活パターンを把握されて犯罪に活用されてしまう危険性もあります。そのため、運用には高度なセキュリティと高い防犯意識が必要となります。
スマートグリッドの実際の導入事例
スマートグリッドは、再生可能エネルギーの普及や脱炭素化の流れを受けて、日本各地で導入が進んでいます。ここでは、代表的な国内のスマートグリッド導入事例を紹介し、地域ごとの取り組みや成果を解説します。
東京電力:全国規模でのスマートメーター導入
東京電力では、2014年以降スマートメーターの本格導入を進め、2020年度までに約2,700万台を家庭や事業所に設置しました。
これにより、電力使用量のリアルタイム把握やピーク時の需要管理が可能となり、電力需給の最適化や業務効率化に大きく貢献しています。スマートメーターのデータ活用により、デマンドレスポンスや節電行動の促進も期待されています。
トヨタ自動車:クルマと住宅をつなぐスマートグリッド
トヨタは「トヨタ スマートセンター」を核に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、HEMSを備えた住宅をつなぐスマートグリッド実証を進めています。
トヨタスマートセンターとは、住宅や車、電力供給事業者、ユーザーを結んで、エネルギー消費を統合管理するシステムで、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の利用する電力も含めて管理する点が特徴です。
スマートフォンから家電や空調を遠隔制御できる仕組みを導入し、再生可能エネルギーの効率的利用とCO₂削減・利用者の利便性向上を両立させました。
小田原市:マイクログリッドによる独立運用
神奈川県小田原市では、「地域マイクログリッド構築事業」が行われています。
太陽光発電と大容量蓄電池を組み合わせ、公園エリア内で自立的に電力を供給する仕組みを導入。2021年秋から稼働し、災害時には独立した電力供給源としても活用できます。
これは「スマートグリッド+防災」の新しいモデルケースとして注目されています。
(参考)小田原市 | 地産地消型の地域マイクログリッド構築事業について
浪江町(福島県):復興スマートコミュニティ
東日本大震災からの復興を進める福島県浪江町では、「復興スマートコミュニティ構築事業」が実施されています。
太陽光発電やEV、CEMS・BEMSを連携させ、非常時でもエネルギーを確保できる体制を整備。
災害対応力の強化と地域経済の活性化を両立させる取り組みとして評価されています。
スマートグリッドのこれからの展望
スマートグリッドは、電力の安定供給と効率的なエネルギー利用を実現するための次世代インフラとして、今後さらに発展していくことが期待されています。特に、脱炭素社会の実現や再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、その重要性は一層高まっています。
1. 再生可能エネルギーとの融合強化
太陽光や風力といった再生可能エネルギーは発電量が天候に左右されやすく、従来の電力網では安定供給が難しい課題がありました。スマートグリッドでは、AIによる需要予測や分散型電源の制御により、再エネを最大限に活用しつつ安定した電力供給を維持する仕組みが整備されつつあります。
2. 蓄電池・EVとの連携拡大
家庭用蓄電池や電気自動車(EV)は、スマートグリッドの中で「移動可能な蓄電池」として活用が進んでいます。余剰電力を充電し、需要ピーク時や災害時に放電することで、電力需給の平準化と地域レジリエンスの向上に貢献します。今後はV2G(Vehicle to Grid:車から電力網への供給)技術の普及が進み、電力システムの柔軟性を高めると見込まれます。
3. AI・IoTによる高度なエネルギーマネジメント
スマートメーターやIoTセンサーから得られるリアルタイムデータを活用し、AIが需要予測や負荷調整を行うことで、効率的なエネルギー配分と無駄のない電力利用が可能になります。これにより、需要家側でも省エネの最適化やコスト削減が期待されます。
4. 地域エネルギーマネジメント(CEMS)の拡大
スマートグリッドは個々の家庭や企業だけでなく、地域全体を対象とする「CEMS(Community Energy Management System)」と結びつき、分散型エネルギーの地産地消モデルを推進します。これにより、災害に強く、かつ環境負荷の少ない持続可能な街づくりが可能になると考えられます。
まとめ
スマートグリッドはこれからの持続可能な社会を形作る上で欠かせない物です。その中でHEMSやBEMSといった家庭やビル内での電力管理の取り組みを紹介しました。エネルギーの無駄遣いを防ぎ効率化を行うため、HEMSやBEMSの導入を検討しましょう。
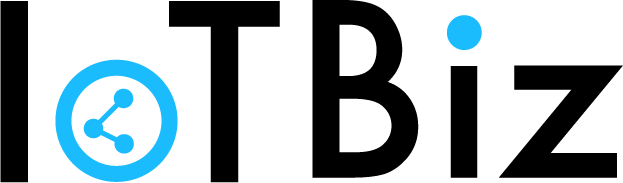
IoTBiz編集部
2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。
関連記事

ニュース
スマート〇〇
DX
この記事では、株式会社LIXILと株式会社リベロエンジニアにより開発された、ピッキング作業に向けたスマートグラスを活用したシステムについて紹介しています。
2025-10-29
2min

Wi-Fi
スマート〇〇
出張・旅行先のホテルで、Wi-Fiが繋がらない状況に陥ってしまい、苦い経験を覚えた方は多いでしょう。この記事では、ホテルでWi-Fiが繋がらなくなる原因や、Wi-Fiが繋がらない状況に陥った際の対処法について解説しています。
2025-09-19
4min
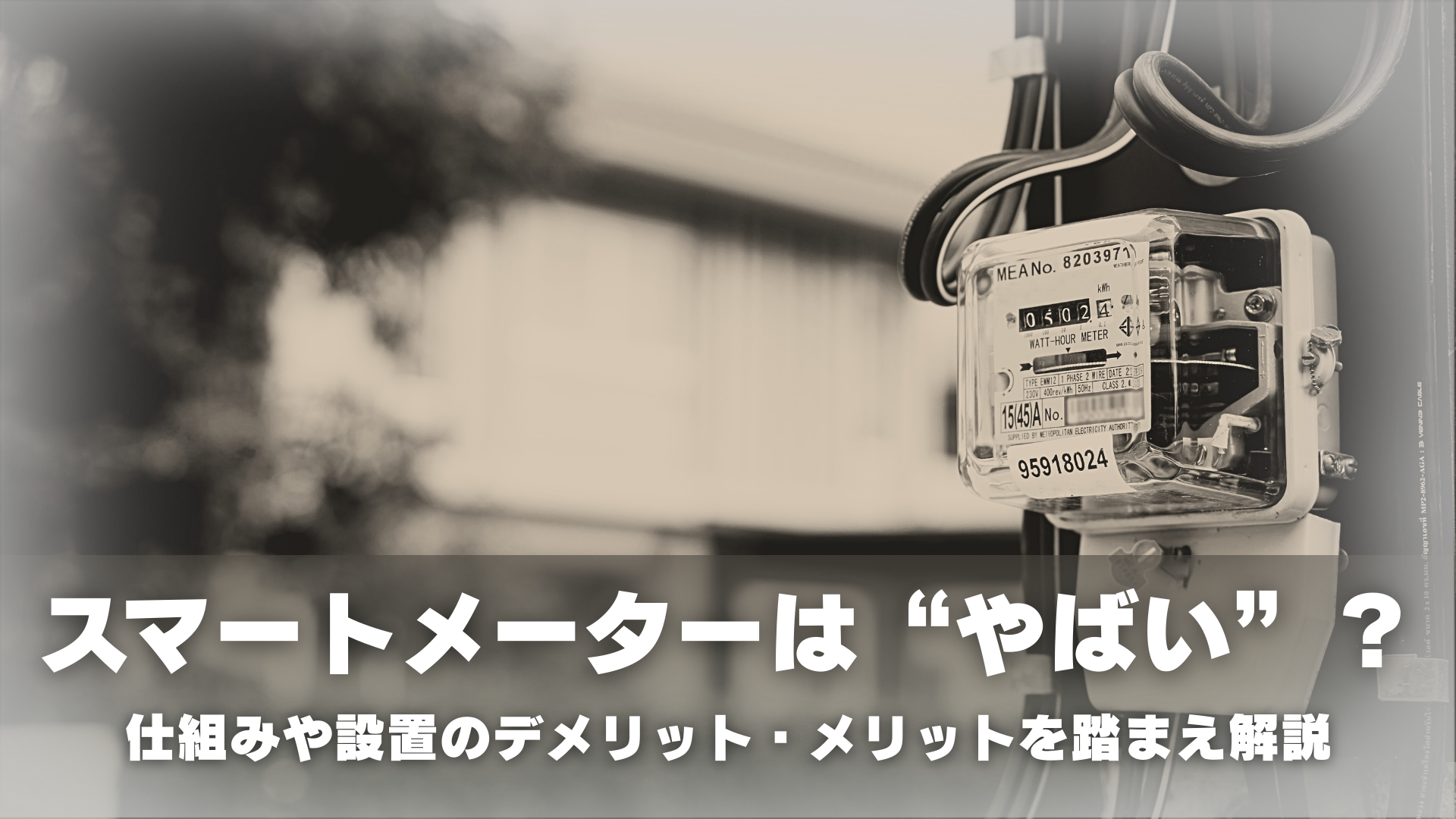
スマート〇〇
IoT
M2M
この記事では、スマートメーターをデメリットとメリットの観点から、本当に“やばい”かどうかについて解説しています。
2025-09-03
7min