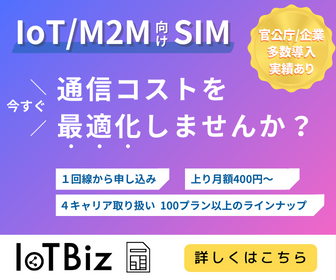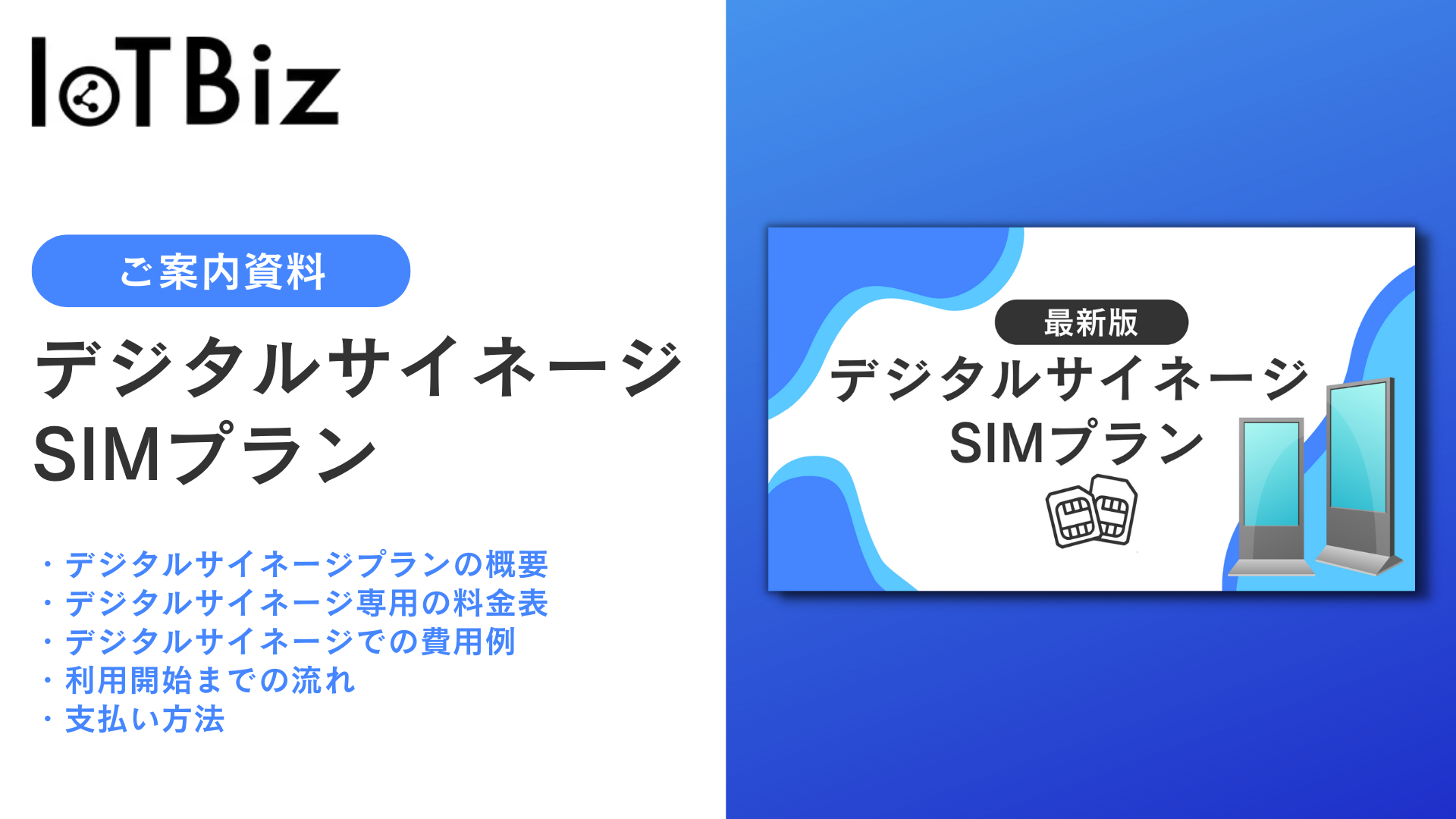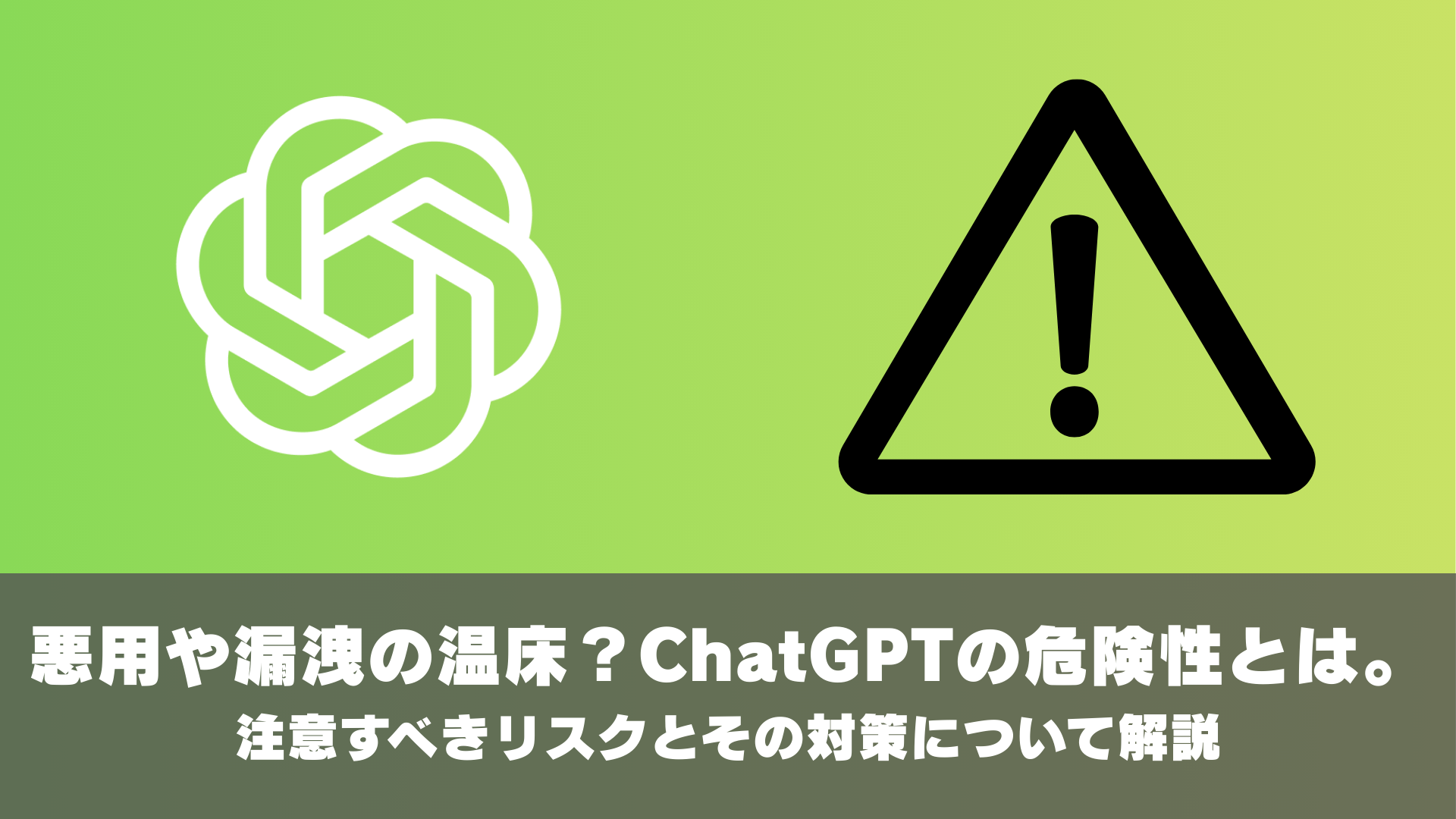WiFi 6とは?特徴やメリット、デメリット、利用する際の注意点を解説
WiFi 6とは?特徴やメリット、デメリット、利用する際の注意点を解説

近年、よく耳にする次世代WiFi規格である「WiFi 6」について、その基本情報や仕組み、メリットについてご紹介します。WiFi 6は、従来のWiFiとどのように異なるのでしょうか?また、WiFi 6が私たちの生活にどのような変化をもたらすのでしょうか?
目次
WiFi 6とは
WiFi 6は、次世代の無線通信規格であり、「wifi6」「WI-FI6」「11ax」などと表現されることがありますが、正式には「WiFi 6」または「IEEE 802.11ax」と表記します。従来のWi-Fi規格に比べて、高速かつ高効率なデータ転送を実現するために開発されました。
まずは、WiFi 6の特徴や課題などを紹介します。
そもそもWiFiとは
WiFiは「ワイファイ」と読みます。スマホやPC、タブレットなどの端末を無線でLAN(Local Area Network)に接続する技術のことです。自宅や職場、カフェなどでWiFiを利用するには、専用のWiFiルーターが必要です。
WiFi 6の特徴
WiFi 6の導入により、高速かつ安定した無線通信環境が実現され、デバイス間の接続やインターネット利用の品質が向上することが期待されています。WiFi 6は、主に以下の特徴を持っています。
①高速性
WiFi 6は、従来のWiFiよりも高速なデータ転送が可能です。これは、多くのデバイスが同時に接続されている状況でも、高速な通信が維持されることを意味します。
②高い容量
WiFi 6では、周囲のデバイスの数に関係なく、より多くのデバイスを同時に接続することができます。これにより、混雑したネットワーク環境でも安定した接続が可能になります。
③低遅延
WiFi 6は、遅延を最小限に抑えるために設計されています。リアルタイムの応答性が求められるアプリケーションやサービス(オンラインゲームやビデオ通話など)において、よりスムーズな体験を提供します。
④エネルギー効率
WiFi 6は、デバイスのバッテリー寿命を延ばすための機能も備えています。省電力モードやターゲットワイクアップ(デバイスが一時的にスリープ状態から復帰するタイミングを合わせる機能)などの技術により、エネルギー効率が向上します。
WiFiの歴史
歴代のWiFi規格について、「世代」「名称」「規格名」とそれぞれの主な特長(最大通信速度・周波数)を1つの表にまとめて紹介します。
| 世代 | 名称 | 規格名 | 最大通信速度 | 周波数 |
|---|---|---|---|---|
| 第6世代(2019年~) | Wi-Fi 6 | IEEE 802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz帯 / 5GHz帯 |
| 第5世代(2013年~) | Wi-Fi 5 | IEEE 802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz帯 |
| 第4世代(2009年~) | Wi-Fi 4 | IEEE 802.11n | 600Mbps | 2.4GHz帯 / 5GHz帯 |
| 第3世代(2003年~) | - | IEEE 802.11g | 54Mbps | 2.4GHz帯 |
| 第2世代(1999年~) | - | IEEE 802.11aIEEE 802.11b | 54Mbps11Mbps | 5GHz帯2.4GHz帯 |
| 第1世代(1997年~) | - | IEEE 802.11 | 2Mbps | 2.4GHz帯 |
WiFi 6のメリット
WiFi 6の特徴や、WiFiの歴史をご理解いただけましたか?ここからは、WiFi 6の主なメリットを紹介していきます。
今よりも早い高速通信が利用できる
WiFi 6はWiFi 5に比べ、最大通信速度が約1.4倍も高速化されています。これにより、高画質な映像や大容量データの転送が迅速に行えます。
複数端末を同時で利用できる
「直交周波数分割多元接続(OFDMA)」技術を採用し、複数デバイスの同時接続が可能となりました。これにより、同時に多くのデバイスがネットワークを利用しても効率的に通信できます。
電力の消費を抑えることができる
「Target Wake Time(TWT)」技術を利用して、通信が不要な時は機器をスリープモードに切り替えることで、バッテリー寿命を延ばし、省エネ効果が得られます。
これまで以上にセキュリティを強化できる
新しいセキュリティ規格である「WiFi CERTIFIED WPA3」が導入され、WPA2よりも強固なセキュリティが提供されます。セッションキーの生成が通信ごとに異なり、高いセキュリティ性が実現されます。
周波数帯域の柔軟な利用ができる
2.4GHz帯と5GHz帯の両方の周波数が利用でき、電波の状況に合わせて適切な周波数に接続を変更することで、より快適なネットワーク利用が可能です。
WiFi 6のデメリット
WiFi 6には多くのメリットがありますが、いくつかの課題や注意点、デメリットも存在します。ここからは、WiFi 6の主なデメリットを紹介します。
対応デバイスが多くない
WiFi 6は新しい規格であり、全てのデバイスが対応しているわけではありません。古いデバイスや低価格なものは恩恵を受けられないため、全てのデバイスがWiFi 6に対応する必要があります。
コストが増加する
WiFi 6に対応したデバイスやルーターは、従来の規格に比べて高価であることがあります。初期導入時には新しい機器を導入するための費用がかかります。
周波数帯域を制限されることがある
高速通信を実現するためにWiFi 6は広い帯域を利用しますが、一部の地域や環境では周囲の通信機器や障害物により制約が生じます。これにより最適なパフォーマンスを引き出すことが難しくなる可能性があります。
実際の速度との差異がある
WiFi 6は理論上の最大速度を提供しますが、実際の使用環境ではネットワークの混雑や信号の減衰、デバイス間の距離などにより、実際の速度は低下することがあります。
WiFi 6で採用された4つの新技術
WiFi 6に初めて採用された4つの新技術を紹介します。

TWT(Target Wake Time)
1つ目は、「TWT(Target Wake Time)」です。
TWT(Target Wake Time / ターゲット起動時間)とは、WiFi 6(IEEE 802.11ax)で導入された省電力機能です。TWT自体はIoT端末向けの無線LAN規格であるIEEE 802.11ah(WiFi HaLow)で導入されていましたが、WiFi関連では初めてWiFi 6に導入されました。
MU-MIMO(Multiple Input Multiple Output)
2つ目は、「MU-MIMO(Multiple Input Multiple Output)」です。
MIMO(Multiple Input Multiple Output)とは、送信機と受信機の双方が複数のアンテナを使い、同一の周波数帯で同一通信を行うことで、周波数帯を増やさず通信速度を高速化したり、通信距離を拡大したりできる技術のことです。このMIMOは、接続するデバイス量が増えると通信速度が低下してしまうデメリットがあります。
MU-MIMOは「Multi User MIMO」の略称で、MIMOの中でも複数のデバイスに同時にデータ送信できる技術のことです。MIMOのデメリットであった同時接続における通信速度の低下を防ぎ、通信速度の高速化を維持できるのが特徴です。
Spatial Reuse
3つ目は、「Spatial Reuse」です。
Spatial Reuse(SR / スペーシャル・リユース)とは、混み合った通信環境で、通信の品質を向上し、他の無線ルーターの電波があっても混線せずに通信させる技術のことです。
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
4つ目は、「OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)」です。
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access / 直交周波数分割多元接続)とは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)をベースにした無線通信⽅式の⼀種で、複数のデバイスを接続できるようにする技術のことです。
WiFi 6を利用する際の注意点
WiFi 6を導入する際には、対応したデバイスやルーターの選択が重要です。同時に、有線接続の場合にはLANケーブルはカテゴリ6A以上を使用しなければ、十分な性能を発揮できない可能性があるため、注意が必要です。
WiFi 6は下位互換性を持っていますが、対応したルーターを使用していても非対応のデバイスと通信できます。したがって、環境が整うまで下位互換性を利用して通信が可能です。ただし、通信の規格は従来と同様であり、WiFi 6のメリットを享受することはできません。
WiFi 6対応のスマホについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
『』
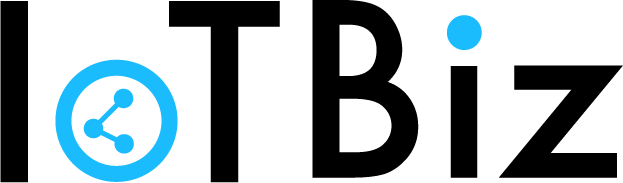
IoTBiz編集部
2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛けるDXHUB株式会社のビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。
関連記事

Wi-Fi
IPv4が繋がらないのにIPv6だけ繋がる原因と対処法を解説。二重ルーターやIPv4 over IPv6の設定不備、DNS設定ミスなど主な原因を特定し、ルーター再起動やブリッジモード変更などの具体的な解決策を紹介します。
2026-01-27
7min

Wi-Fi
マンションでWiFiが繋がらない原因と対処法を徹底解説。デバイスやルーターの問題から電波干渉、回線混雑まで、7つの原因と具体的な改善策を紹介します。
2026-01-23
7min

Wi-Fi
WiFi規格9種類(11a/b/g/n/ac/ax/be/bn/ah)の違いを徹底比較。各規格の通信速度・周波数帯・特徴をわかりやすく解説し、ビジネス用途別の選び方も紹介します。
2026-01-20
7min